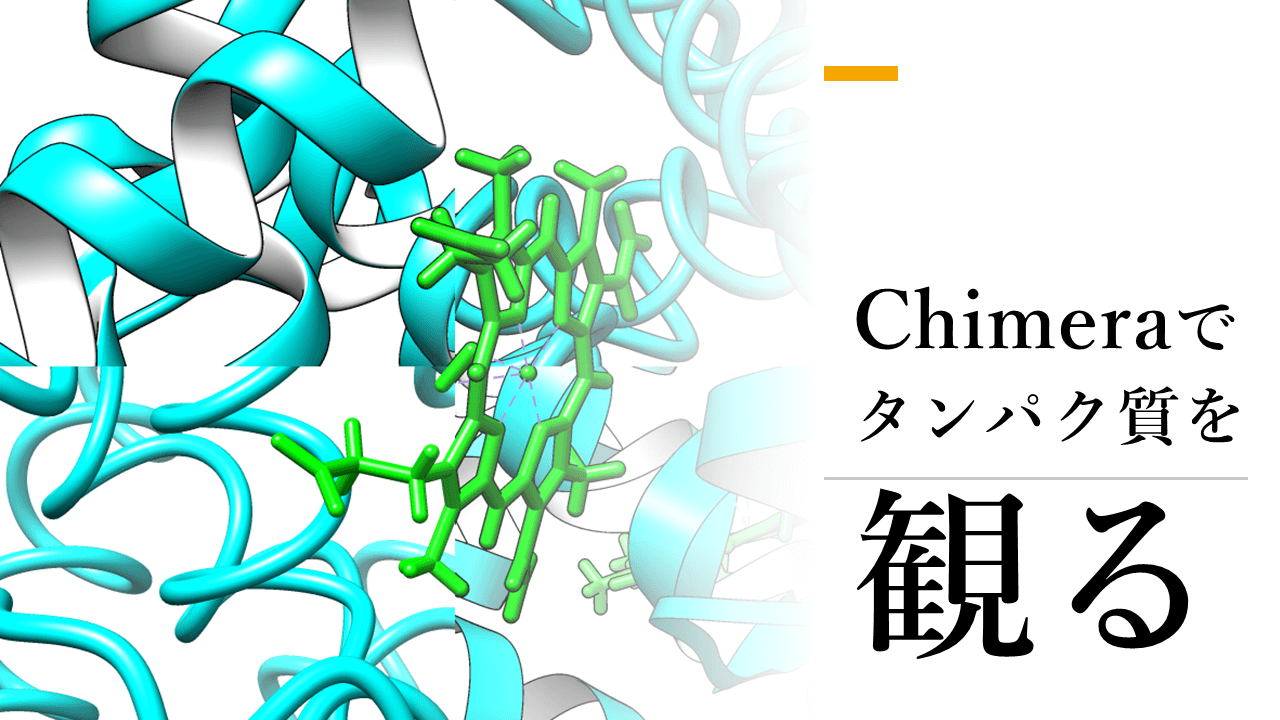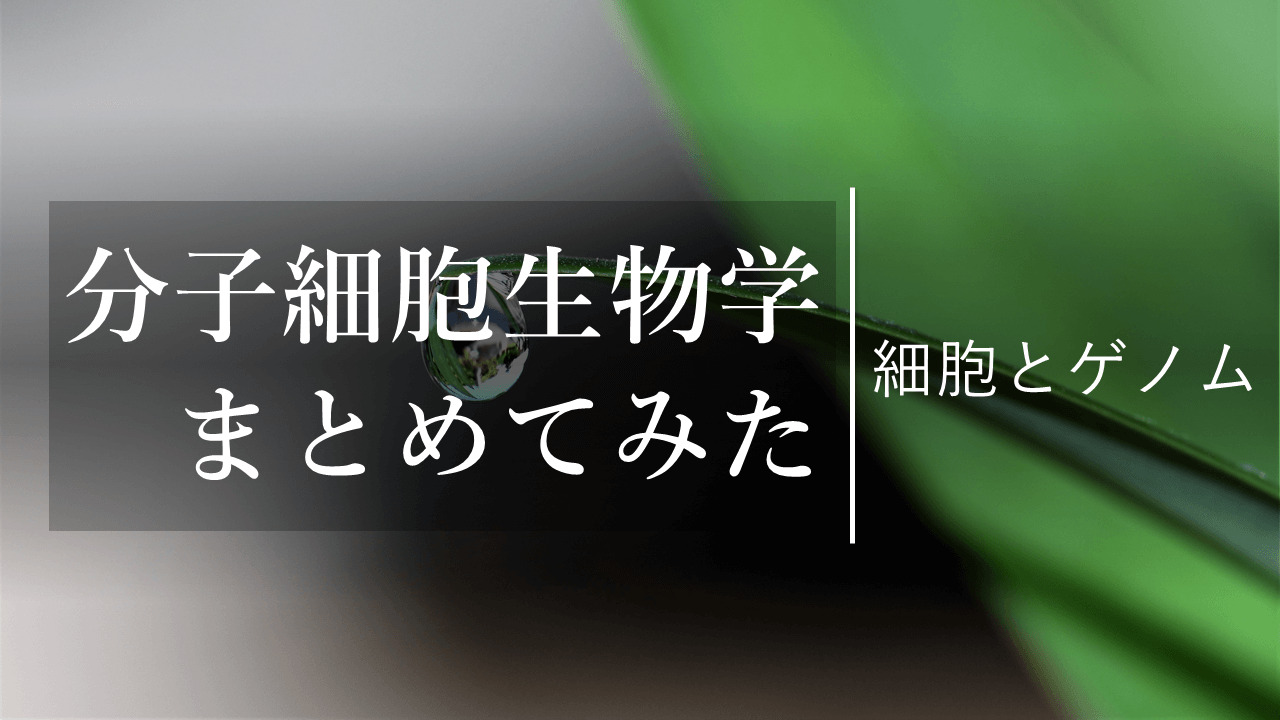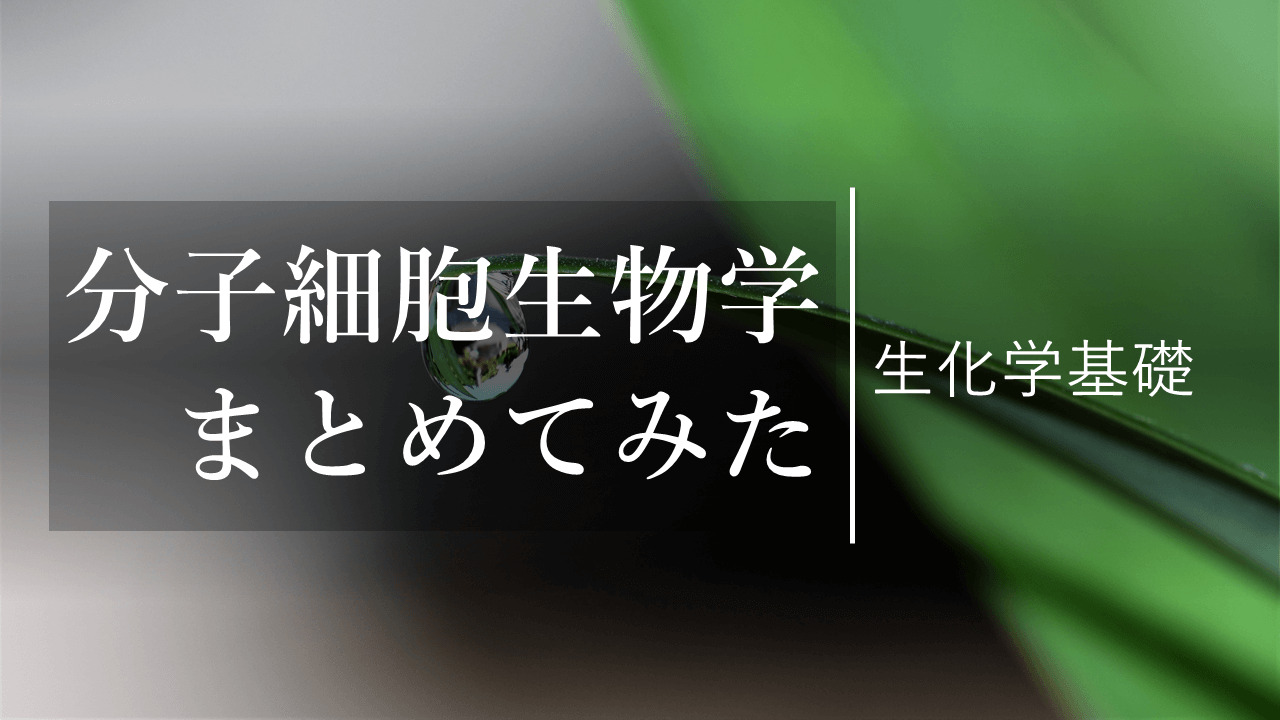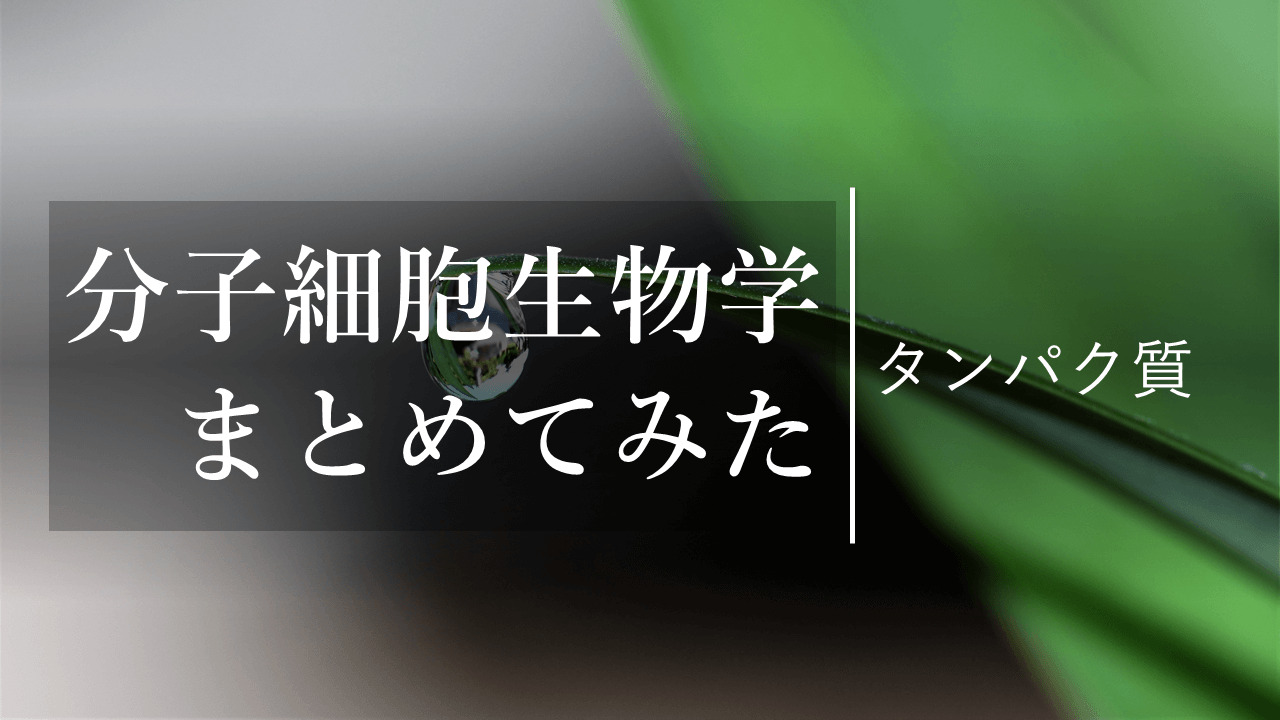DNAの複製
DNA複製の主な機構
DNAは大変安定な分子であり、熱運動によって千切れるたり、勝手に塩基が変わったりすることは無いと考えて良い。その他の要因で変異が入る確率も大変低く、遺伝子でも調節領域でもないところへの変異や同義コドンを考慮すると、アミノ酸配列が変わる変異はもっと稀である。大腸菌では細胞1世代あたり1010塩基対あたり3つ、人の生殖系列では細胞分裂1回あたり1010塩基対あたり1つ程度の確率である。
変異率が生物の複雑さの上限を決めるという考え方がある。生存に必要なタンパク質の種類が多ければ多いほど、変異によって生体を維持できなくなる確率が上昇する。今の地球上での変異率だと、必須タンパクの数が3万程度の生物の複雑度で限界だという。もし今より10倍程度変異頻度が高かったら、使用可能遺伝子数の上限は3千となり、進化はショウジョウバエより前で頭打ちだったであろうという推定もある。
DNAポリメラーゼはDNAを極めて正確かつ高速(1000塩基/秒)に複製するが、5’から3’の方向にしかDNAを伸長できない。そのため、二本鎖を切り開きながら新生DNAを合成していくとすると、一方の鎖については連続して伸長できるが、もう一方の鎖については開裂する方向と逆向きに合成していく必要がある。DNAの開裂が進んでいくとポリメラーゼの後方に1本差が露出いていき、ある程度の長さがたまると、後ろに戻って新しく合成を始める。鋳型鎖の開裂の方向に連続して新生DNAの合成が行われる方の鎖をリーディング鎖、後ろ向きに何度も合成する方の鎖をラギング鎖といい、ラギング鎖に形成する新生DNA断片を岡崎フラグメントと呼ぶ。DNAポリメラーゼには、合成中の岡崎フラグメントの最後の塩基の3’末端と隣の岡崎フラグメントの5’末端をつなぐ機能はない。こうしたニックはDNAリガーゼによって繋がれる。
DNAポリメラーゼの校正機構:正しい対の塩基を伸長するほうが、遷移状態も生成物も安定なので、そもそも正しい伸長のほうが間違った伸長より起こりやすい。また、もし間違った塩基をつないだ場合、正しい塩基対が形成されないために次の伸長が非常に進みづらくなる。この間に、DNAポリメラーゼの分子中か別のサブユニットにある校正用3’→5’エキソヌクレアーゼが誤った塩基を取り除く。時折正しい塩基対に対してもエキソヌクレアーゼが働いてこれを取り除くこともあるだろうが、正しい塩基なら生成物が安定な分、間違った塩基のときより反応速度は遅いと考えられる。伸長は正しい塩基のほうが速く、除去は間違った塩基のほうが速いことで、全体的に正しい塩基を付加し続けることになる。この自己修復機能の鍵は、誤った付加が起こると次の付加が起こりづらくなる点である。1つ前の正しい塩基対が形成する構造が、DNAポリメラーゼの理想的な配座と次の付加の遷移状態の安定化に影響していると考えられる。したがって、DNAポリメラーゼは1つ前の正しい結合がないと次の反応を進められない。このことは、合成の開始時にDNAポリメラーゼの足場となる二重鎖部分が必要であることを示唆している。
転写反応でRNAポリメラーゼがRNAを伸長していく際は、DNAポリメラーゼと違い1つ前の正しい結合を必要としない。したがって、RNAポリメラーゼはプライマーがなくても伸長を開始できるが、エキソヌクレアーゼを用いた校正はできない。誤った結合を作った後でもその次の反応が進むからである。しかし、校正ができなくても転写の際にはDNA複製ほどは問題にならない。
DNAへのdNTP付加反応は、付加されに来るdNTPの加水分解エネルギーで駆動されている。リン酸基は5’についているので、前のヌクレオチドの3’と次のヌクレオチドの5’を繋いでいるということになる。もし、3’→5’に伸長していた場合、ミスを犯してエキソヌクレアーゼが塩基を1つ取り除いたとすると、露出する5’末端にはもう三リン酸は存在しないので、ここで反応が止まってしまう。このため、エキソヌクレアーゼを用いた校正を行う以上は、5’→3’へと合成する他に選択肢はないのである。
DNA複製に関わるその他のタンパク質
リーディング鎖の最初のプライマーとラギング鎖の岡崎フラグメントごとに必要となるプライマーはDNAプライマーゼによってRNAを用いて作られる。プライマーゼは鋳型しか無いところからプライマーを作る必要があるので、1つ前の正しい結合などは全く参照しない。したがって、機構の性質上ミスが起こりやすいので、一旦RNAで作っておいてから、後で一律取り除いてより正確なDNAポリメラーゼに作り直させるというやり方を採用した。RNAを取り除く作業は、特異的DNA修復酵素が担う。
DNAポリメラーゼは岡崎フラグメント同士を結ぶことはできない。ポリメラーゼは最後の塩基を付加したところで遊離して、DNAリガーゼがATPを消費して、フラグメント同士の結合を形成する。
DNAヘリカーゼが鋳型の二重螺旋をほどく役割を担っている。このタンパクはドーナツ型で、中央の輪に一本鎖DNAを通すようになっている。ヘリカーゼは、ATPを加水分解して自身の構造を変え、元に戻るときに力学的な仕事として塩基対の水素結合を切断する。ドーナツの輪に入れる鎖は二本鎖の内どちらでも良い。DNAヘリカーゼは5’→3’と3’→5’のどちらに動いてもその役割を果たすことができるからだ。実際にどちらの方向にも動くヘリカーゼが確認されているが、どうやらラギング鎖上を5’→3’に動くものが主流らしい。
滑る止め金タンパクは、ドーナツ型をしており、一本鎖DNAを穴に通してかつDNAポリメラーゼと結合することで、DNAポリメラーゼが飛んでいかないようにしている。さらに、止め金装着タンパクというのがいて、止め金タンパクを変形させて一本鎖DNAに挟み込む。このとき、もちろんATPを消費する。
一本鎖DNA結合タンパク(SSB:single-strand DNA binding protein)は、ヘリカーゼによって引き裂かれてできた一本鎖DNAに結合して、鎖が自己相補的な部分でヘアピンを作らないようにしている。このタンパクは塩基部分を覆わないので、ポリメラーゼはSSBが結合したままのDNAを鋳型として使える。このことから逆に、ポリメラーゼの方も主鎖の方とはあまり相互作用していないの考えられる。
DNA複製に関わるタンパクたちは、統率の取れた複合体を形成している。特にラギング鎖ではプライマーの作成、止め金装着、DNA合成を何度も行わなくてはならないので、過程に関わるタンパクを予め集合させておくことで、全体の効率を飛躍的に向上させている。
複製ミスの修復
エキソヌクレアーゼが見逃した不正な塩基は、その後の校正系が正す。非相補的な塩基対があると、その部分でだけ主鎖の螺旋のねじれ方が異なるので、この構造を認識して結合するタンパクが存在する。しかし、不正な塩基対を探し出せたとして、1つ大きな問題に直面する。例えば、A-Cという塩基対を発見したときに、Aが正しいと信じてCを修正するか、反対にCが正しいと信じてAを修正するかはどのように判断すればいいのだろうか。つまり、どちらが鋳型でどちらが新生のDNAかを判断しなければならないのだ。この判別に、細菌と真核細胞では異なる機構を用いている。
- 細菌の場合:DNAに含まれるGATCという配列のAは基本的にメチル化されている。ただし、このメチル化は新生DNAが合成されてからしばらくしないと起こらないので、メチル化されていない方の鎖が修復すべきものだとわかる。
- 真核細胞の場合:ラギング鎖のおいては、岡崎フラグメント上のニックの存在を頼りに新生鎖を見極めている。ニックのある方が新生鎖であると判定できる。しかし、リーディング鎖ではどうしているのか不明。
真核細胞の修復系で働くMutSとMutLの機構:これらのタンパクは、非共有結合して複合体となっている。まず、MutSが誤った塩基対の構造を認識して結合する。MutLは不対合の場所からDANを手繰り寄せていき、ニックを探す。ニックから一本鎖を引き剥がしていき、不対合のところを切断すれば不正な塩基を含むDNA断片が遊離する。生じた空白はDNAポリメラーゼとリガーゼが通常の機構で埋める。細菌ではMutLの代わりにMutHがメチル化されていないGATCのAを探して、ここから不対合のところまで除去する。
DNAの複製中、ヘリカーゼが二重螺旋を引き剥がしながら進むため、親DNAにねじれ歪がたまっていく。これを解消するタンパクが存在する。
- トポイソメラーゼI:親DNAに一時的にニックを作る。ニックの両側でDNAは自由に回転できるので、歪が解消されるまで回る。このタンパクは全過程でATPを消費しない。鎖を切断するときに自身の内部のチロシンのOHでリン酸エステルを形成し、エネルギーをここに保存している。鎖をつなげるときには、保存していたエネルギーを用いる。
- トポイソメラーぜII:DNAに超螺旋ができたり、二本のDNAが絡まったりしたときに、一方の鎖を切断してもう一方の鎖を通したあと、最初の鎖をつなぎ直す。これにより、超螺旋や絡まりが解消される。
細菌と真核生物のDNA複製系は、リーディング鎖、ラギング鎖、岡崎フラグメントなどの基本的な流れは共通している。関わるタンパクもよく似ているが、真核生物の方が種類が多かったり、一つ一つが複雑だったりする。このため、真核生物の方が複雑な動作(制御)ができる。また、真核細胞のDNAはヒストンに巻き付いていることも忘れてはならない。
DNA複製の開始と終了
これまで、DNA複製の途中の機構のみで、始まりと終わりの話をしていなかった。複製フォークのでき方と開始の調節、真核生物特有の問題を論じる。
DNA複製起点は数百塩基対の決まった配列で、A-Tが多い。A-TはC-Gに比べ、水素結合の強度が2/3程度なので、開きやすいのだろう。複製起点から両側に複製フォークは進んでいく。
大腸菌のDNAは4.6×106bpの環状で、複製起点が1箇所存在する。まず。開始タンパクが何分子も複製起点に結合して、その近辺の二重螺旋を緩める。塩基同士の水素結合が外れるまで構造が変化し、一本鎖DNAが露出する。ここにDNAヘリカーゼとヘリカーゼ装着タンパクが寄ってきて、ヘリカーゼが装着される。装着されたヘリカーゼがDNA上を進みながら、一本鎖部分を長くしていく。十分な長さの一本鎖が露出したら、プライマーゼがプライマーRNAを合成して、さらにポリメラーゼと他の複製関連タンパクが集まって複製フォークが完成する。それぞれのフォークが半周して、DNA複製が完了する。
大腸菌は、DNA複製に必要な栄養(dNTP)が十分得られない状態では複製を開始しない。また、二回連続で複製しないように、①DNA螺旋を歪める開始タンパクは一度任務を果たすと自身に結合しているATPを加水分解してしばらくの間不活性な構造に変化し、②GATC配列のAがメチル化されるまでタイムラグがあることを使用している。メチル化されるまで阻害タンパクSeqAが結合して開始タンパクがDNAを開けなくする。ちなみにDamメチラーゼという酵素が全てのGATC配列のメチル化の責任を負う。
真核生物の場合:大腸菌のDNAは短いので2つの複製フォークでおよそ30分程度で複製が完了するが、我々の場合はそうはいかない。ヒトは3万から5万の複製起点を使用している。複製起点そのものはもっと多く存在しており(おそらく10倍程度)、分化した細胞ごとに異なる位置を使っているらしい。真核細胞の細胞周期はS期(合成期)→G2期→M期(分裂期)→G1期→S期となっているが、S期になった途端に一斉に複製が始まるわけではない。周囲のクロマチンの凝縮度も関わって、複製起点ごとに合成開始の時期が異なる。クロマチンの凝縮度は複製起点が使われるか否かや、開始の速度には影響するが、複製フォークが進む速さにはあまり関係がないらしい。フォークの前方でヒストンを解体しているためである(後述)。
複製フォークの形成は、細菌の場合、特定の塩基配列に開始タンパクが集まって一本鎖を露出し、ここに諸々のタンパクが順次集合するという流れだった。出芽酵母以外の真核細胞は大分異なるやり方をしている。まずは、細菌と比較的よく似ている出芽酵母から説明する。出芽酵母の複製起点は全体的にATが豊富で、①複製起点認識複合体(ORC:origin recognition complex)という巨大な複合体が結合する配列と②ORCの結合を助けるタンパクが結合する配列が含まれる。G1期の時点でORCとヘリカーゼは装着済みで、待機状態となっている。S期に入ると、キナーゼの量が増え、ORCとヘリカーゼがリン酸化される。リン酸化による構造変化はORCにとっては不活化、ヘリカーゼにとっては前進開始を意味する。ORCはリン酸化されてもDNAに結合したままでいられるが、その隣にヘリカーゼは装着されないようになっている。一旦G2期→M期を経て、次のG1期になるまでリン酸化は解けないので、全DNAを必ず1回だけ複製できる。
ヒトの複製起点はいくつか見つかっており、塩基配列も判明しているが、それらを比較してもこれが複製起点だというコンセンサス配列は見つかっていない。個々の複製起点と思われる配列を、染色体の別の場所に移動させても、その場所のクロマチンがそれなりに緩ければ、正しく機能するという。ヒトも出芽酵母のORCと似た複合体を用いている。
真核生物ならではの問題として、DNA複製と同時に大量のヒストンも合成しなければならない。大部分の一般的なタンパク質は細胞周期に関わらず常に合成され続けているが、ヒストンはS期に集中して合成される。遊離のヒストンの量とDNA合成開始を検知して、ヒストンを司令するmRNAの合成と分解を制御する機構があるのだろう。
複製フォークが通過する際、前方でヒストン8量体はH3-H4四量体と2つのH2A-H2B2量体に解体され、二量体は遊離し、4量体の方はDNAにゆるく結合したままらしい。4量体は二本の新しい鎖にランダムに乗っていき、空白は新たに合成された4量体が埋める。ここに、ヒストンシャペロンが2量体を結合させて、ヌクレオソームが完成する。
真核生物は直鎖状のDNAを使用しているために、末端処理の問題が発生する。DANポリメラーゼは5’→3’の方向にしか合成できず、1つ前の正しい3’末端が必要であることを思い出そう。プライマーゼが作ったプライマーRNAを分解して、DNAポリメラーゼが作り直すということだったが、ラギング鎖の5’末端ではその次の岡崎フラグメントの正しい3’が存在しないため、ポリメラーゼは末端のDNAを合成できない。このまま端を修復できないでいると、DNAは複製のたびに新しい鎖の末端がどんどん短くなっていくだろう。細菌はDNAを環状にすることでこの問題に対処した。一方、真核生物は端を伸ばしていく別のタンパク質を用意するという方法を採用した。DNAの末端はテロメアと呼ばれる短い配列を何度も繰り返した配列で、ヒトの場合GGGTTAである。テロメラーゼは自前のRNAを内部に持っていおり、これを鋳型にしてDNAの端を伸ばしていく。相補鎖は通常の機構で合成される。やはり、最終的にできる末端は一本鎖が露出しているが、元の長さは回復している。
テロメアの末端の露出している一本鎖は正常な構造だが、DNAが事故で千切れて生じた末端と区別がつかず、修復機構により変なふうに修復される恐れがある。テロメアが反復配列であることを利用して、一本鎖部分を内部の二本鎖を引き裂いて挿入し(t-ループ構造)、シュテレリンというタンパクキャップにより、修復を受けないように保護している。特定のタンパク質がt-ループ構造の形成と維持に関わっている。
テロメアと寿命:テロメアの長さは複製のときに削れていく速さと、テロメラーゼが伸ばす速さで決まる。これらの速さは変えずに、テロメアの長さを変えたDNAを酵母細胞に導入したところ、平均より長いDNAを導入した場合でも短いDNAを導入した場合でも、細胞分裂を繰り返すと、平均の長さになった。これはテロメアの長さがよく調節されている証拠である。一方、多細胞生物の体細胞のほとんどは削られる速さの方が速いため、分裂のたびにテロメアは徐々に短くなっていく。そのうち、テロメラーゼが認識する配列が削られ始め、最終的にはDNA損傷応答が働き、それ以上分裂しなくなる。ヒトの線維芽細胞は普通60回ほどしか分裂できないが、テロメラーゼ遺伝子を導入すると、無限に分裂できるようになる。反対にマウスのテロメラーゼ遺伝子を落とすと、最初のうちは正常だが、世代を重ねるに連れ、早期に老化したり腫瘍がよくできるようになる。(マウスのテロメアはもともと長いので、はじめの世代では問題にならなかった)