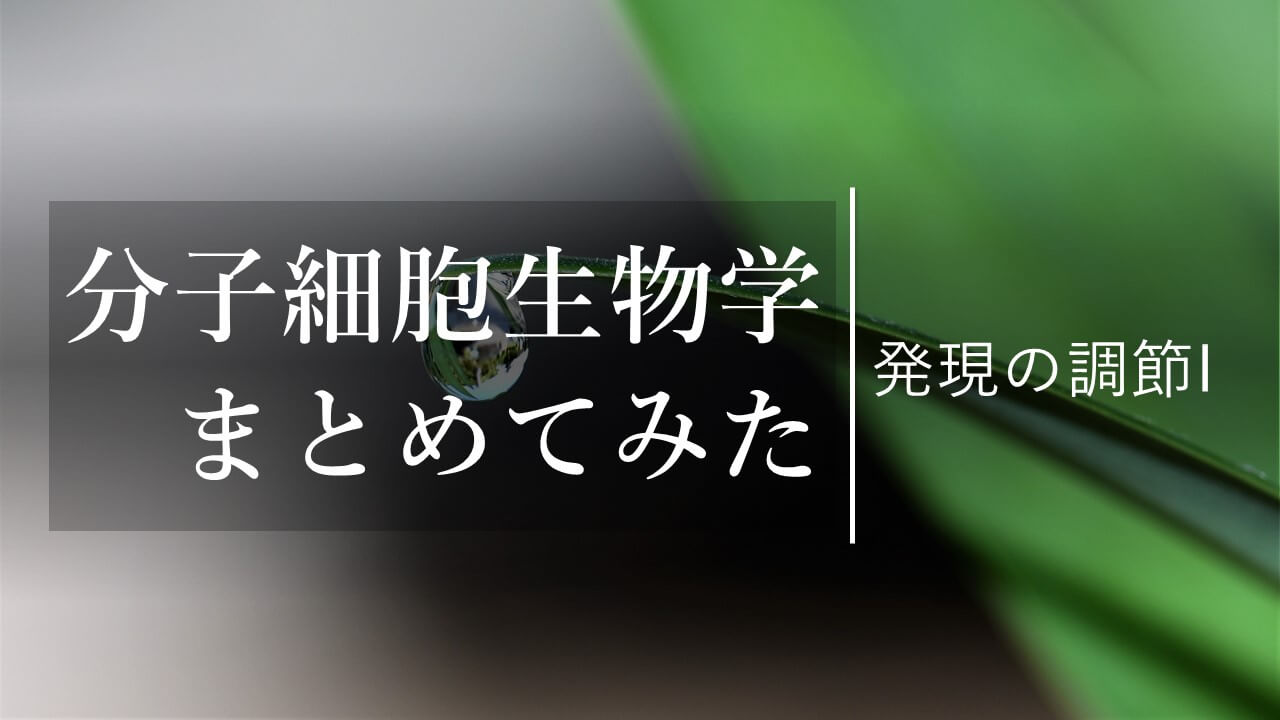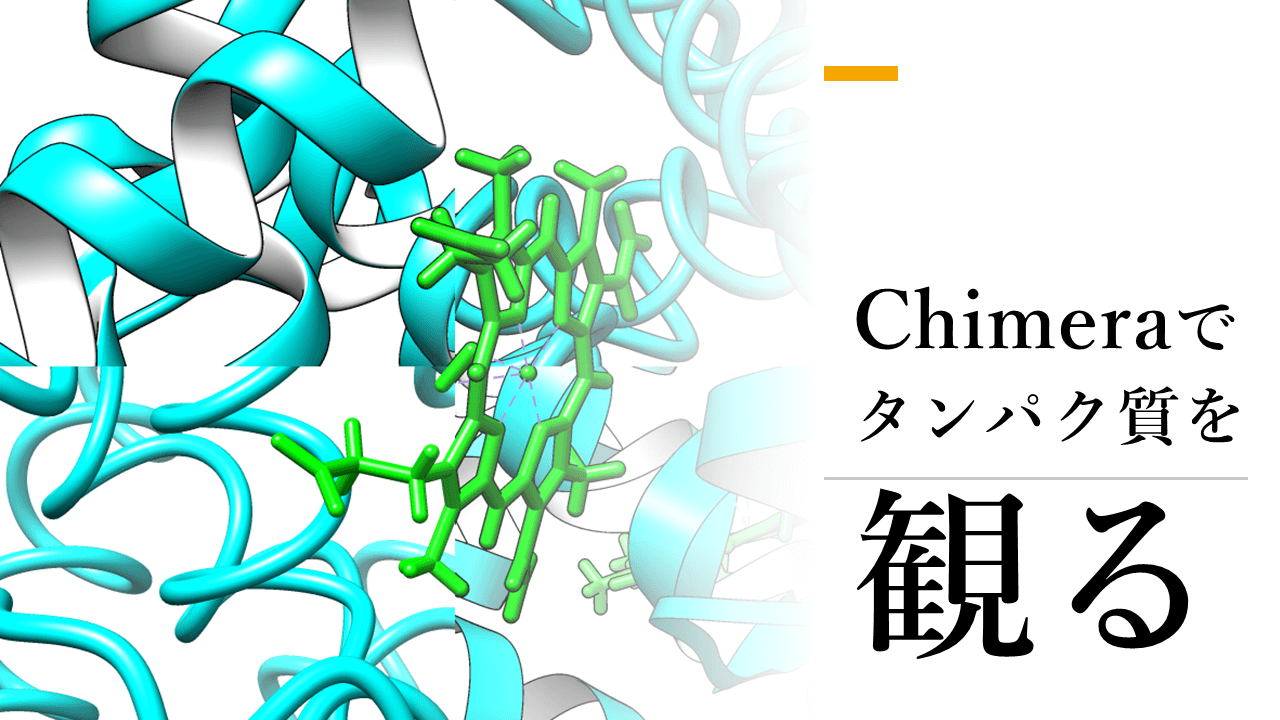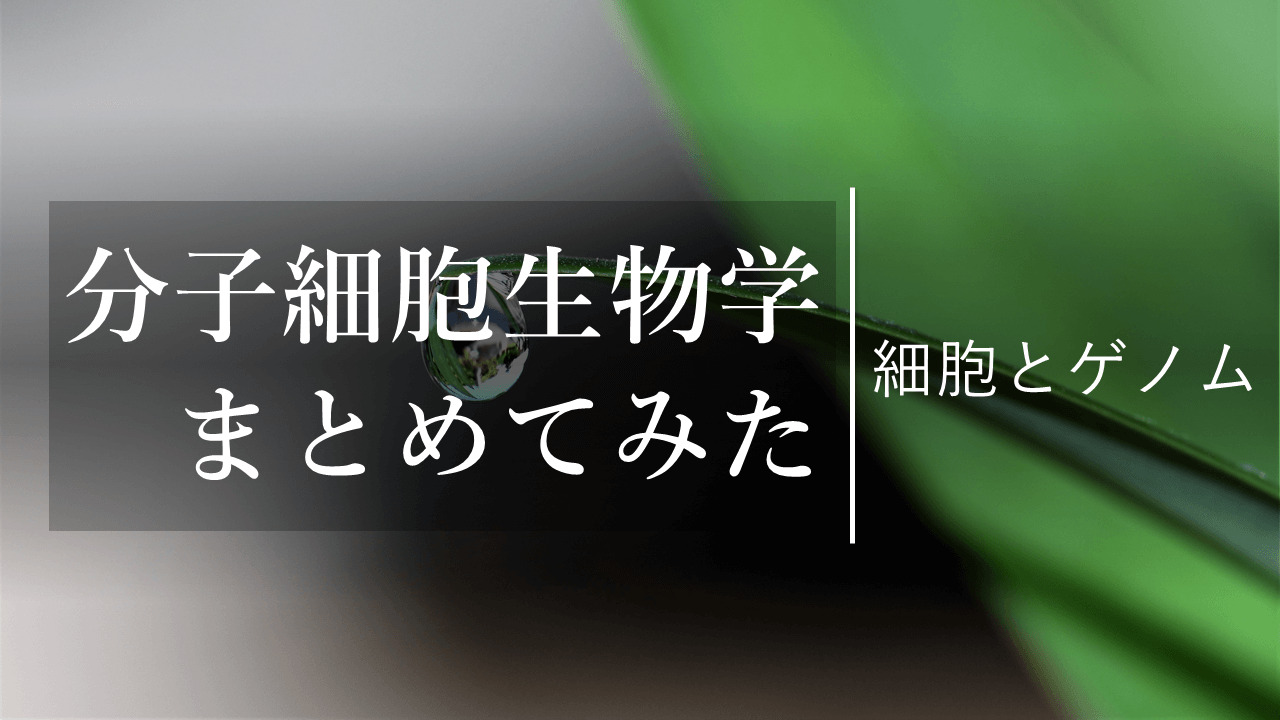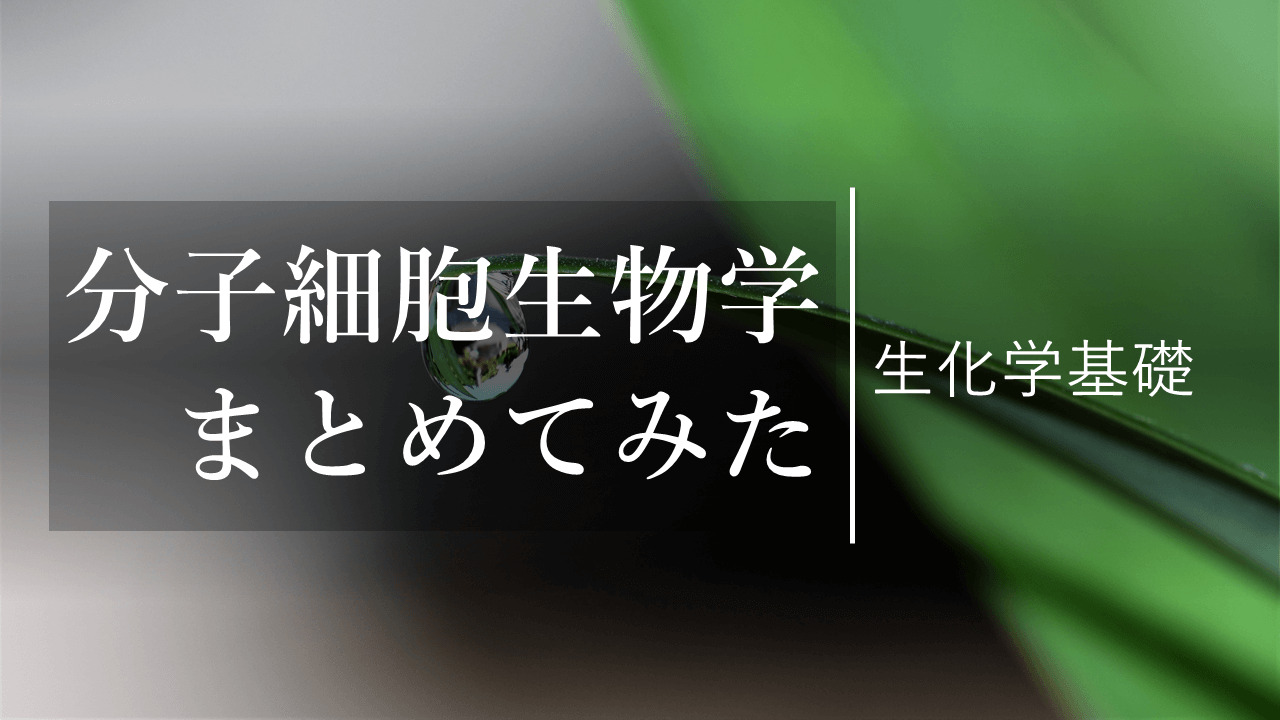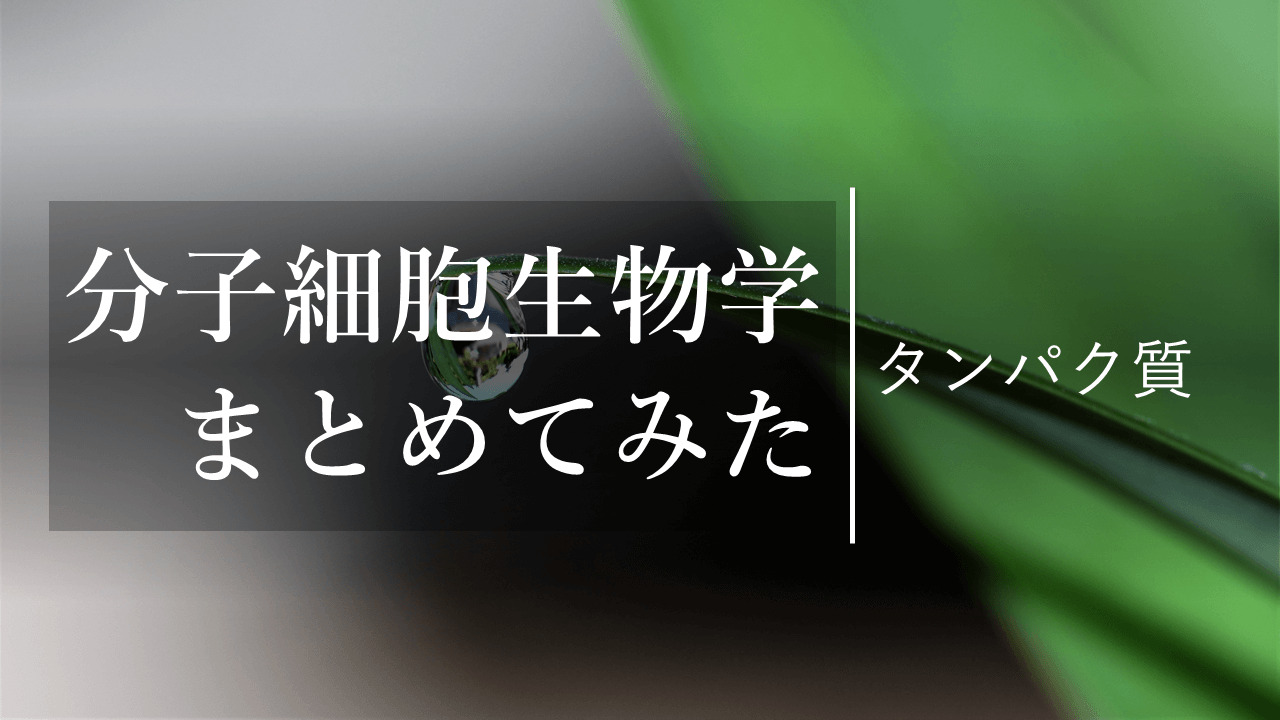発現の調節I
細胞の遺伝子発現はよく調節されているが、ごく一部の例外を除いてDNAには手を加えずに行われる。細胞の分化や環境の違いにより、発現する遺伝子が大きく異なるが、塩基配列は変化していない。分化した細胞の核を、無核の未受精卵に移植すると完全に正常な個体となる。転写、RNAプロセシング、RNAの核外への輸送、翻訳の開始、mRNAの分解、タンパク質の活性調節とありとあらゆる段階で遺伝子発現が調節され得る。
転写開始の調節
調節される遺伝子と同じDNA上にあるシス調節配列にタンパク質(転写調節因子)が結合して、遺伝子の転写頻度を調節している。転写調節因子の多くは、二重螺旋を開かずに、側面から塩基配列を認識している。調節因子が結合する配列は唯一つと決まっているわけではなく、近しい配列に異なる親和性で結合しうる。また、調節因子が2量体を形成してより広い表面積で塩基配列を認識することも行われる。二種類の調節因子が2量体を形成する際、ホモ2量体二種類とヘテロ2量体1種類作れるので、三通りの特異性が生じる。
ヌクレオソームの構造も転写調節因子との結合性に関わる。基本的に、ヒストンに巻き付いている部分に対しては親和性が低い。2種類の調節因子が順番に働いて、協同的結合が促されることもある。例えば、1つ目の調節因子がヒストンからDNAを緩めて、2つ目の調節因子が強く結合できるようになるなど。
比較的単純かつ非常に有名な大腸菌の例から見ていこう。トリプトファン・リプレッサーと呼ばれる調節因子は、トリプトファンと結合するとプロモーター近くの調節配列に結合するようになり、トリプトファン合成酵素の転写を阻害する。これは、単純に調節因子が邪魔でRNAポリメラーゼがプロモーターと結合できなくなることによる。トリプトファンの濃度が下がると、リプレッサーに結合していたトリプトファンが外れ、この形態だとリプレッサーはプロモーターに強く結合できないのでDNAから乖離する。すると、RNAポリメラーゼがプロモーター領域に接近できるようになり、トリプトファン合成酵素の転写が行われるようになる。
リプレッサーとは反対に、転写を活性化する因子も存在する。転写を活性化するには、RNAポリメラーゼとプロモーターとの結合を邪魔しない場所から、RNAポリメラーゼと非共有結合する表面を提供すればいい。
細菌では複合体を成す各酵素がDNA上でも隣接していて、一本のmRNAとして転写される例が多く知られている。そういった遺伝子群をオペロンと呼ぶ。ラクトースを分解してエネルギー源にするためのLacオペロンもその1つである。Lacオペロンには、転写の活性と抑制のどちらの機構も存在する。大腸菌はグルコースが不足しているとき、cAMP(環状アデニン一リン酸、サイクリックAMP)を合成する。CAPと呼ばれる因子はcAMPと結合すると、DNAの所定の場所に結合してLacオペロンの転写を促進する。一方、ラクトースが細胞内に少ないときにはLacリプレッサーが転写を妨害している。整理すると、グルコースが無くかつラクトースが有るときだけLacオペロンが転写されることになる。グルコースが有るときはグルコースを使用し、ラクトースが無いときにはそれを分解する酵素は作らない。
調節配列は多くの場合対象の遺伝子の近くにあるが、中には離れた位置に存在して、結合した調節因子がDNAループを介して転写開始に作用する例もある。DNAループは細菌では珍しいが、真核生物では頻繁に見られる。細菌では調節因子がRNAポリメラーゼに直接作用していたが、真核生物では調節因子は介在因子に作用して、間接的にRNAポリメラーゼの挙動を制御する。介在因子は転写開始に必須で、多くの転写基本因子、転写調節因子、RNAポリメラーゼIIの適切な相互作用を保っている。膨大な数の調節因子が介在因子と相互作用しており、それらの総合で転写の促進か抑制かが決まる。ある調節因子が複数の遺伝子の調節に関わっていて、あちらの遺伝子では活性化、こちらでは抑制の効果をもたらすといったことが普通に行われている。
クロマチン再構成複合体やヒストンシャペロン、ヒストン修飾酵素が転写開始の様々な段階で関与し、転写開始の時期を調節できる。ヒストンへの修飾やヘテロクロマチンへの置換は、すぐにもとに戻る場合もあれば、しばらく持続することもあり、細胞は遺伝子の発現パターンを長期的にも短期的にも保持することができる。ヒストンへの修飾が転写因子を集合することもある。
RNAポリメラーゼをプロモーターから開放して転写を開始させる因子や、停止しているポリメラーゼを再稼働させるタンパクもいる。事前に必要な準備を済ませて発進待機状態にしておくことで、プロモーターに色々な因子が集合する時間を飛ばして、シグナルに素早く応答することができる。
転写の開始に関わる複数の因子の効果の総合は、和というより積と見るべきである。ある2つの因子がともに活性化エネルギーを下げて、速度を10倍にする効果を持つなら、2つ合わされば速度は100倍になる。
細菌の転写の抑制の手法は、ポリメラーゼがプロモーターと結合するのを妨害するくらいしか挙げられないが、真核生物の場合、転写の開始機構が複雑な分、色々な方法がある。
- 抑制因子が活性因子と競合的なDNA配列(一部が重なっている)に結合して活性因子が適切な場所に結合できなくする。
- 活性化因子に結合して、活性化因子の介在因子と相互作用する面を隠蔽する。
- 転写基本因子と結合して、より直接的に転写開始を妨害する。
- クロマチン再構成複合体や修飾酵素を誘導して、ヌクレオソームをいじる。
真核生物の転写活性化はDNAループを介した遠距離からの活性化が多いので、間違って別の遺伝子の転写を活性化しないような仕組みがある。インサレーター配列に結合するタンパクが適切なループ形成を誘導し、活性化タンパクが活性化してほしくないところには触れなようにする。
多細胞生物の分化:複雑な転写調節ネットワークが調節因子の適切な濃度を生じ、目的の遺伝子を適切な時期に発現させる。Lacオペロンの調節のように、調節因子が協同的に働くことで、AND回路、OR回路、フリップフロップ、フィードバックを用いた制御を実現できる。下流に多くの遺伝子を従えている少数のマスター調節因子の発現を調節することで、細胞の形態を劇的に変化させることができる。
転写調節は外部からのシグナルに依存することもある。細胞の分化とは、本質的にはいくつかのシグナルのON/OFFが永続化することである。正のフィードバック回路は、一度受けた外部からの分化指令を永続的に記憶することができる。
DNAにメチル基を付加することでシグナルを記憶する仕組みがある。共有結合は勝手には切れないから、この細胞記憶は極めて頑強である。5′-CG-3’のシトシンが相補鎖のものも合わせてともにメチル化される。メチル化によりDNAの表面の形が変わり、その配列と結合する因子が結合できなくなったり、反対に結合できるようになったりするが、多くの場合、DNAのメチル化は遺伝子の不活性化を指令しているらしい。メチル化によって結合できるようになった因子が、ヒストン修飾酵素を誘導して、クロマチンの凝縮度を変えることもある。DNAのメチル化はDNA複製の際に維持メチラーゼによって娘鎖に継承され、子孫細胞も同じ発現パターンを示す。
初期胚のときにそのDNAが精子由来か卵子由来かによって異なるメチル化を受け、ある遺伝子は父親由来の配列が転写されやすく、また別の遺伝子は母親由来の配列が転写されやすいといった現象がある。これはゲノムの刷り込みと呼ばれる。刷り込みが進化上どのように有利だったかはまだわかっていない。
クロマチンの構造として情報が記録され、子孫細胞にこれが伝わることもある。哺乳類の雌個体は発生の初期に2つあるX染色体の内の片方を封印して、以後使わないようにする。染色体のX不活性化センターと呼ばれる部位でXistと呼ばれるRNAが合成されて、これが染色体全体に広がっていく。この様になった後、ヒストン修飾酵素やその他のタンパクが集合してクロマチンを密に凝縮させて、抑制状態にしていると考えられている。
DNAのCのメチル化やクロマチン構造として情報が伝わることをシスなエピジェネティック、シグナル小分子や特定の構造のタンパク質が細胞質に浮遊して子孫細胞に伝わることをトランスなエピジェネティックと呼ぶ。