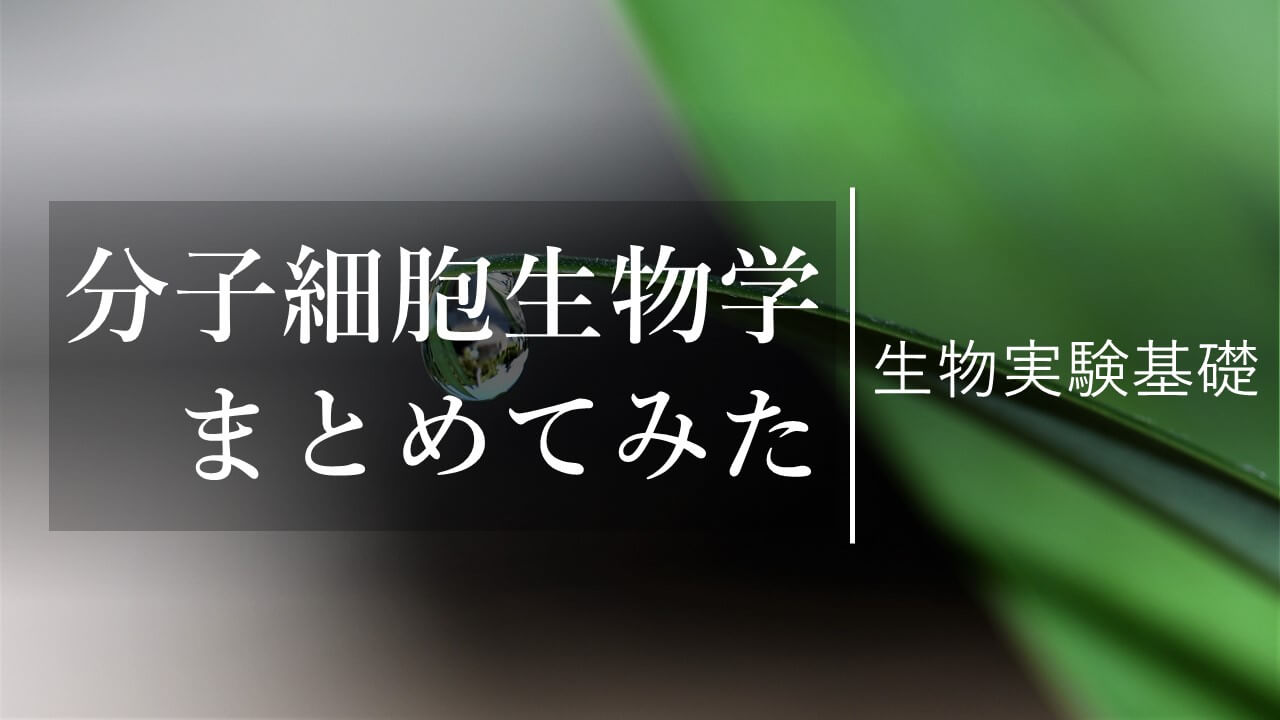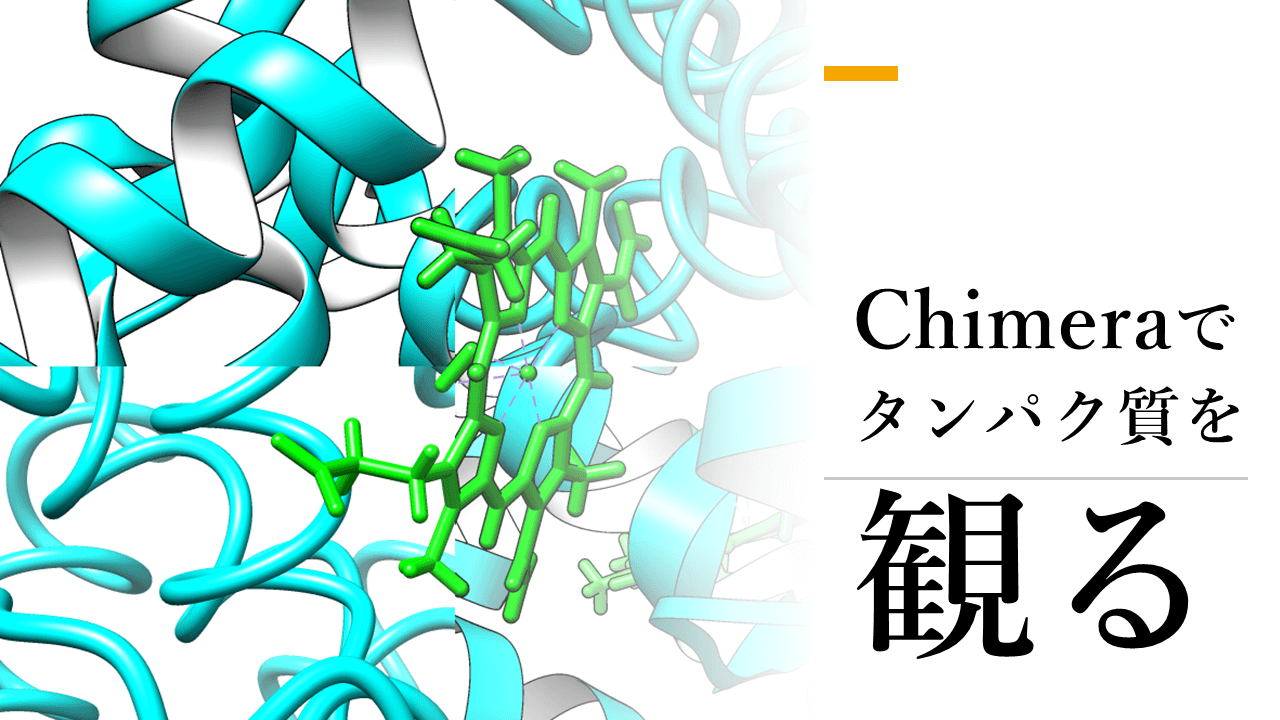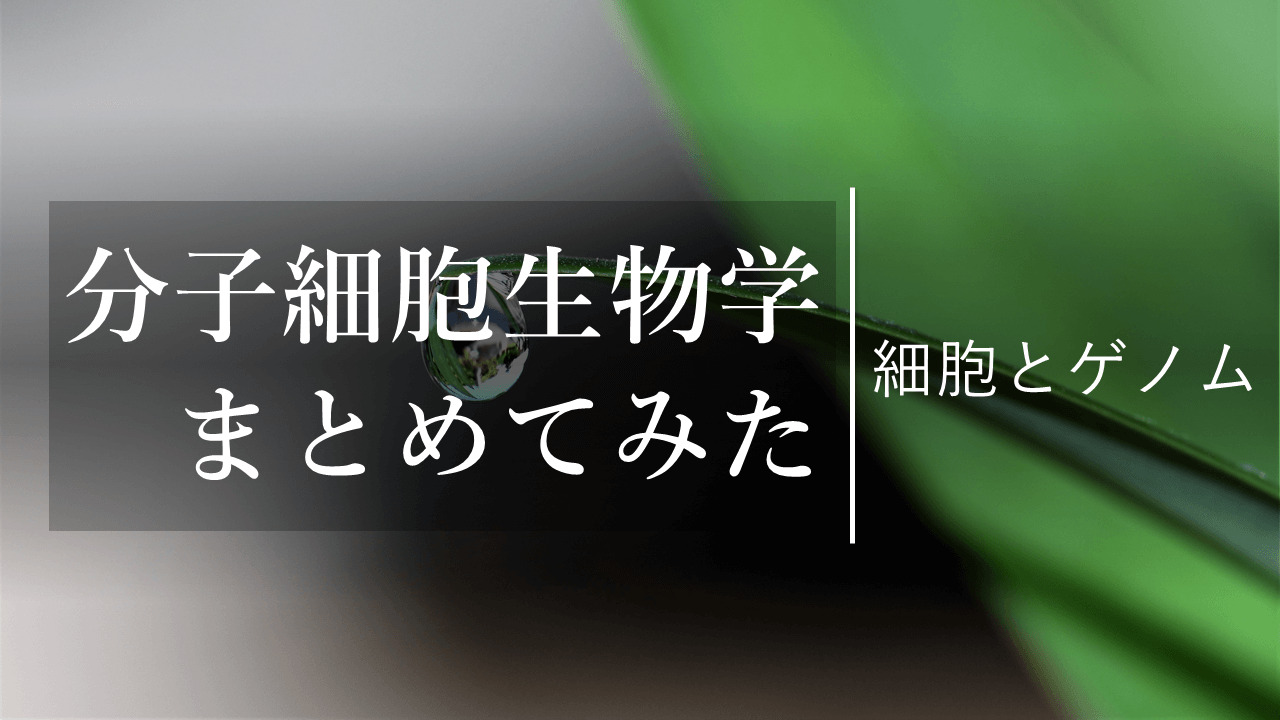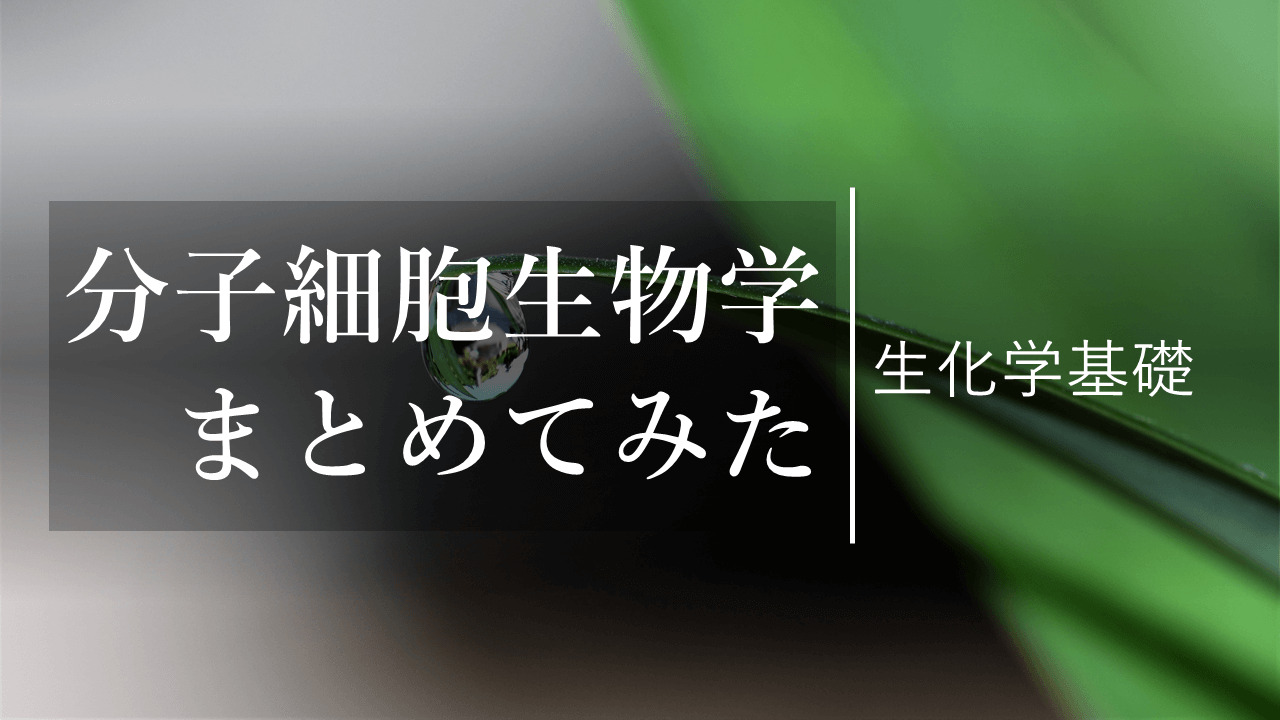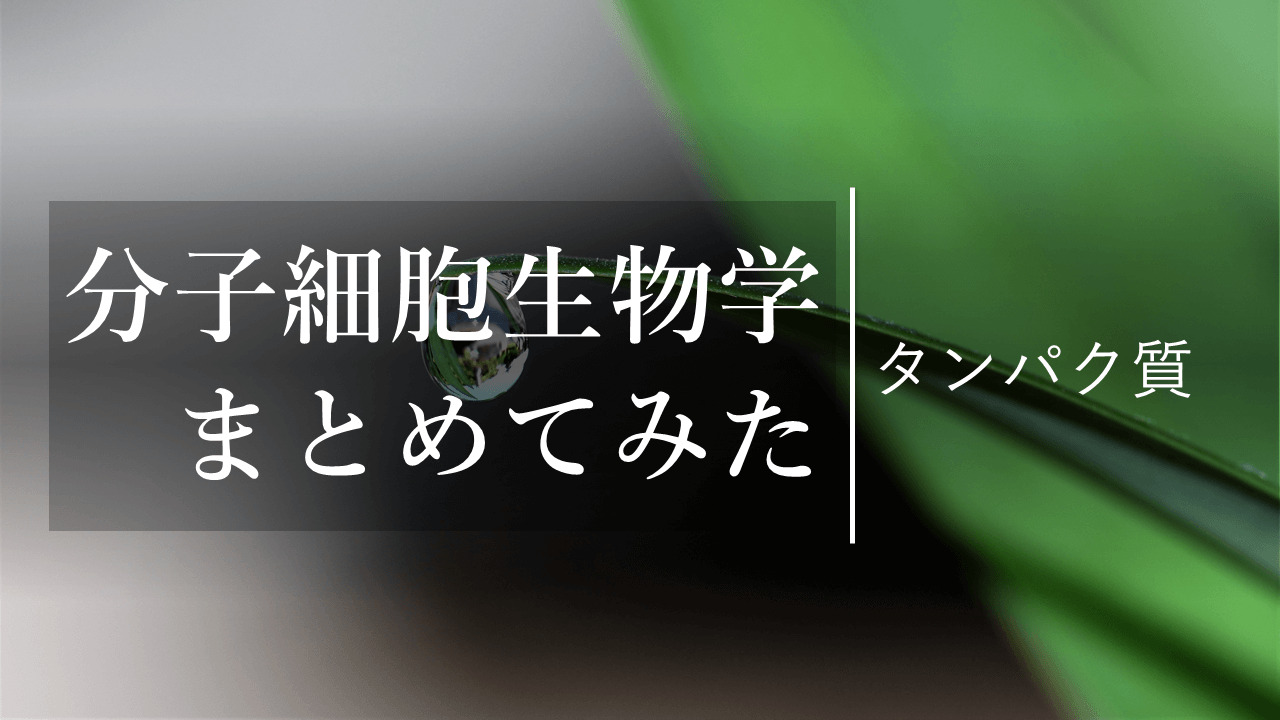生物実験基礎
生体からの試料の単離
生体組織から興味ある細胞を単離する最初のステップは、細胞同士を接着している細胞外マトリックスると細胞の結合を切り離すことである。細胞外マトリックス中のタンパク質の分解にはトリプシンやコラゲナーゼを用い、Ca2+を介している結合にはEDTAを用いてCa2+を取り除くのが効果的である。その後、穏やかに撹拌して様々な細胞が入り混じった遊離液を得る。次に、目的の細胞に結合する蛍光標識付き抗体を混ぜる。セルソーターはレーザーでこの蛍光標識を検出することができる。まず、超音波ノズル振動装置が1つの液滴に1個以下の細胞が入るように液滴を作る。次に、落下していく最中に蛍光を発する液滴にのみ電荷を付与し、さらに下で電場を通過させて液滴を分離する。この装置は大変正確で、毎秒数千個の細胞を分離することができる。
組織から単離してきた細胞をそのまま研究に用いてもよいが、培養細胞の方が均一性が高く扱いやすい。培養は何回も繰り返すことが可能で、数ヶ月にも渡って継代させることができる。培養細胞でも元の組織の一部であるかのように分化後の性質を示すことが多い。永久に分裂できる細胞も有るが、多細胞生物のほとんどの細胞は分裂回数に制限がある。テロメアーゼを発現させたり、発癌遺伝子を導入したりして不死化することができる場合がある。また、がん細胞から研究用の細胞を作り出すこともできる。このようにして用意した不死細胞は液体窒素中で長期間保存可能で、解凍後すぐに増殖を再開する。
抗体は唯一つの構造に特異的に結合するので、蛍光標識を付けておけば一種類のタンパク質の動きを観察することができる。抗体は、原始的なやり方では標的のタンパクを動物に注射して抗体を作らせて血清から単離する。この方法は時間と労力を消費するので、1975年に目的の抗体を作り続ける不死細胞、ハイブリドーマ細胞が作られた。抗体を作るB細胞の寿命は限られている。これを不死細胞と融合させて2つの核を持つヘテロカリオンの細胞を作る。次の細胞分裂のときに核膜が消失して、全ての染色体が1つの核に収まって、ハイブリドーマ細胞となる。
細胞を注意深く破砕すると、細胞小器官を無傷に保ったまま細胞膜を破壊することができる。膜はすぐに自発的に閉じて小胞となり、様々な大きさ・密度をもつ小器官を含んだ懸濁液を得る。これをまずはゆっくりと遠心して核などの大きな成分を沈殿させる。上清を取って少し高速で遠心してミトコンドリアを、上清をさらに高速で遠心して小胞といった具合に沈殿を分取する。沈殿を再び懸濁させてから遠心することで純度を上げる事ができる。別の方法として、底に行くほど高密度になるような密度勾配の有る溶液を用意しておき、この溶液の上層から試料を遠心すると、各成分が密度ごとにバンドを形成する。この方法は分離度がよく、分子の含む同位体の違いを区別するほどである。このようにして、興味ある細胞小器官や生体分子を単離して研究に使うことができる。
細胞小器官よりはるかに小さなタンパク質は、クロマトグラフィーで分離することが多い。多孔質の詰まった充填筒に試料を通して、移動度の違いで分離する。各成分は充填剤との吸着平衡に有るが、よく吸着される成分は遅く通過してくる。イオン交換カラムは正か負かのどちらかに帯電していて、反対の電荷をもつタンパク質の移動を遅らせる。アフィニティカラムは生化学的な結合(多数の非共有結合からなる特異性の高い結合)を利用して、特定のタンパクを吸着して保持する。後にこれを溶出すれば、ほぼ純粋なタンパク質が得られる。アフィニティカラムとほぼ同じ原理で、目的のタンパクに結合する抗体を担持したアガロース粒子を混ぜて、遠心して沈殿させてタンパクを回収する方法もある(免疫沈降法)。
目的のタンパクに結合する抗体を用意するのが大変な場合がある。そこで、既知の抗体に結合するペプチドを目的タンパクの末端に挿入しておき、その抗体でこのタンパクを単離する方法がある。挿入したペプチドと目的タンパクの連結部位には、特異的プロテアーゼに切断される配列が仕込まれており、ここを切断することで目的タンパクをほぼ無傷の状態で単離することができる。
SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)では、タンパク質を大きさ(長さ)の違いで分離することができる。異なるタンパクでも似た大きさ・分子量のものがあるので、泳動後にゲルを90°回して、pH勾配の中でもう一度泳動すると、各タンパク質は自身の等電点の場所で止まる。したがって、タンパク質を大きさと等電点の両方で分離する事ができる。分子量も等電点も近接している場合は面倒だが、それは稀である。このように二次元に展開されたタンパク質を、ニトロセルロース膜かナイロン膜に写し取ることができる。ここに蛍光標識された抗体を流すことで、目的のタンパク質のスポットを高感度で検出可能である。(ウェスタンブロッティング)
タンパク質の性質と機能の解析
質量分析法は、タンパクを断片化・イオン化して質量分析を行うことで、タンパク質のアミノ酸配列とアセチル化やユビキチン化などの修飾を正確に検出することができる。生物種ごとにゲノム配列データから全タンパクと生じうる断片の質量が列挙されており、得られた結果をこのデータベースと比較することで、試料に含まれるタンパク質を同定できる。
抗体ビーズで標的タンパクを特異的に取得する際、そのタンパクと結合するタンパクがあればともに精製されるので、質量分析法と組み合わせればあるタンパクと相互作用するタンパクを探すということが可能である。(共免疫沈降法)
タンパク同士の相互作用はほぼ常に結合しているものから、数ミリ秒だけくっついては離れてを繰り返すものもある。光学的な測定は乖離平衡定数(Kd)の推定に役立つ。例えばトリプトファンのようなアミノ酸は弱い蛍光を発しているが、母体のタンパクが別のタンパクと結合することで、わずかに波長や強度が変化することがある。この変化は、感度の良い蛍光光度計によって検出可能である。偏光光度計による測定は、小分子とタンパクの結合の検出に役立つ。蛍光標識した小分子に偏光した励起光を当てると、遊離の小分子は早く回転しているので蛍光は偏光していないが、タンパクと結合している場合は回転が遅いので偏光がある程度保たれている。したがって、蛍光の異方性を測定することでKdを推定できる。蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)は2つの蛍光分子間で、一方の発光スペクトルがもう一方の吸光スペクトルと重なっているときに起こり、1つ目の蛍光分子の吸光波長を当てると2つ目の蛍光分子の蛍光が観測される。FRETは発色団が近接しているときにしか起こらないので、これを用いてタンパク同士の相互作用を検出できる。
タンパクの機能を阻害する小分子は、標的タンパクが他のタンパクや小分子と相互作用する面を隠蔽する形で働く。阻害剤は、アフィニティークロマトグラフィーの吸着剤に用いることで結合するタンパクを探したり、細胞生物学実験において特定のタンパクの機能をON/OFFしたりするのに使われる。
X線回折によってタンパク質の三次元構造を決定することができる。これを行うためには、純度の高いタンパク試料が大量に必要で、X線回折より結晶化に時間がかかる場合が多い。X線回折パターンから決まるのは電子密度分布であり、ここからタンパクの構造を決めるためにはアミノ酸配列の情報が必要である。得られる構造の信頼度は、結晶回折の分解能に依存する。
NMRは溶液中でのタンパクの構造を決めるのに役立つ。X線回折と組み合わせて、数万ものタンパク質の構造が決定されてきて、データベース化されている。何か重要な機能を持っていそうなタンパク質を得たら、まずは似た配列のタンパクが無いか調べると良い。配列や構造がよく似ているタンパクは、機能も似ていることがあり、新規に得たタンパクの機能解明のヒントになる。
DNAの操作
制限酵素による特異的な切断・リガーゼによる連結・クローニングベクターやPCRによる大量複製・配列の解読・任意の配列のDNAの化学合成といった手法を駆使して、自由自在にDNAを操作することができる。
制限酵素は細菌類が外来DNAから身を守るため、これを切断するのに使っていた酵素である。DNAの4~8塩基からなる配列を認識して、特異的に糖-リン酸主鎖を切断する。細菌自身のDNAはAがメチル化されていることで区別可能で、切断しないようになっている。例えばHindIIIは5′-AAGCTT-3’のA|Aを切断する。認識部位は回文になっており、HindIII2量体が相補鎖のAAも切断する。このため、生じる断面には一本鎖部分が露出している。数百種類の制限酵素が知られていて、市販されている。
アガロースかポリアクリルアミドのゲルも使った電気泳動では、DNAを長さに応じて分離することができる。ポリアクリルアミドゲルの方が目が細かいため低分子用で、特別仕様のものなら一塩基の違いでも分離できる。バンドは臭化エチジウムなどのDNAに結合したときだけ発色する色素を用いて検出できる。
クローニングベクターを用いるDNA増幅では、増やしたいDNA断片の両端を制限酵素で切断して一本鎖を露出させ、同じ制限酵素で切断したプラスミドベクター(環状DNA)と混合して塩基対形成を促す。DNAリガーゼでニックを閉じて、目的のDNAが埋め込まれたプラスミドを、DNA透過性の大腸菌(コンピテントセル)に導入して増殖させる。大腸菌が細胞分裂するたびに組み込んだDNAも複製される。溶菌してプラスミドを単離し、はじめに用いたものと同じ制限酵素を用いて目的DNAを切り離し、電気泳動等で精製すれば良い。
研究対象の生体試料から抽出したDNAを増幅してできたサンプルをDNAライブラリと呼ぶ。生体からmRNAを抽出して逆転写・増幅して得たものはcDNAライブラリと呼ぶ。DNAライブラリは遺伝子と非転写領域、イントロンを含むが、cDNAライブラリはmRNAに写し取られる部分のみ含むので、研究によって使い分ける。
DNAは加熱すると一本鎖に開裂し、ゆっくり冷やすと塩基対を再生する。その際、約30塩基対からなるDNA断片(プライマー)を混ぜておくと、一部のDNAはプライマーと塩基対形成して、DNAポリメラーゼによって伸長される形となる。したがって、溶液にDNAポリメラーゼとdNTP(N=A, G, C, T)を混ぜておけばDNAが複製され、複数回加熱と冷却を繰り返すことでプライマー対に挟まれた部分が大量に増幅される。
DNAの配列を読むことは、現在では簡単かつ迅速である。古くからジデオキシ法、サンガー法が用いられていたが、さらに新しい方法も開発されている。
遺伝子の機能の研究
ある生物種について、そのDNA配列が全て決定されたとしても、配列情報だけから機能を予測するのは困難である。計算機でコドンを読んで生じるタンパク質の配列を予測する方法は、イントロンが稀で開始コドンから終止コドンまでが比較的長い読み枠が見つかるときのみ可能である。ランダムな塩基配列なら終止コドンは20アミノ酸に1回程度現れるが、実際のタンパクはこれより長いことが普通なのでORF(Open Reading Frame:開始コドンから終止コドンまで)が長ければ、細胞がその部分をタンパク質に翻訳している可能性が高い。しかし、計算機で遺伝子の候補を列挙したとしても、選択的スプライシングや発現調節まで予測することは困難で、結局実験的に確かめる場合がほとんどである。
タンパク質及びそれを指令する遺伝子の機能を調べる最も手っ取り早い方法は、その遺伝子を欠失させてみて何が起こるか観察することである。遺伝学では他と違った形質をもつ個体を単離して、形質(表現型)とその個体がもつDNA配列(遺伝子型)を対応させていく。
ランダムな変異を誘発して大量の変異体を入手したら、それらの中から目的の表現型をもつ個体を単離しなければならない。簡単な表現型、例えばある栄養素が無いと生きていけない個体が目的なら選抜は簡単だが、学習や行動に関わる変異体が欲しい場合は手の込んだ実験を考えなければならない。変異は機能を喪失させるものと獲得させるものがあるが、大抵の場合、獲得型が優勢形質である。
異なる遺伝子に対する変異だが、表現型は同じに見えるものがある。相補性検定では、一方の変異のホモ接合体と他方の変異のホモ接合体を交配させて生まれた子孫が正常型なら、別々の遺伝子に対する変異であったと判定する。大文字が正常型、小文字が異常型で大文字のほうが優性形質であるとする。ある形質の発現にAもBも両方必要であるとき、2種類の異常型両親から(aa BB)×(AA bb)→(Aa Bb)で生じる子供は正常型である。
遺伝子スクリーニングと相補性検定によって、ある機能の発現に関わる遺伝子が複数見つかったら、次はそれらを指令するタンパク質がどの順番で作用しているかを調べることになる。タンパクの構造や反応機構が分からなくても、ある程度は遺伝子解析で調べることができる。個々の遺伝子を1つづつ欠落させた個体やときに2つ欠落させた個体を用意して、各個体で反応経路のどの段階まで進んだかを解析する。
DNAの配列を安価かつ迅速に読めるようになったことで、ある表現型を生じる遺伝子型(配列)の特定が用意になった。その表現型を示す個体とそうでない個体のDNAのを大量に読んで、比較すれば良い。この方法は、人間の疾患の原因となる遺伝子の特定にも使われている。
ここまで見てきたように、古典的な遺伝学の実験では、まず表現型の違いから出発して、その表現型を生じる遺伝子を突き止めるというものであった。ゲノム編集技術の発達により、遺伝子に特定の変異を導入してその変異が表現型にどう影響するのかを解析する逆遺伝学が可能となった。in vitro合成したDNAを細胞の染色体に組み込むのは多少手間がかかるが、今では様々な変異を導入したマウスが研究に使われている。
細菌がウイルスから身を守るために使ってるCRISPR系のCas9タンパクは、ガイドRNAを持ち、このRNAと相補的なDNA領域と結合してDNAを切断する。切断されたDNAは相同組換えで修復される際、実験者が導入した外部DNAと結合しやすい。この現象を用いて、様々な生物のDNAを位置選択的に改変することが可能となった。
色々なモデル生物で、様々な変異を持った集団を作成する作業が進行(もしくは完了)している。例えば、出芽酵母では遺伝子を1つづつ欠失させた6000の変異体の完全なセットが作成され、購入可能である。各変異株のDNAにはそれぞれ固有のバーコード配列が挿入されており、それがどの変異体か簡単に特定できるようになっている。このライブラリを使えば、ある環境中で生き残った変異体を調べて、どの遺伝子がその環境で有用か不可欠か、あるいは無関係かを特定できる。
RNA干渉による特定のmRNAの不活化は、遺伝子のノックアウトに比べてお手軽な手法である。線虫の場合、不活化したい遺伝子のmRNAの一部と相補的な二本鎖RNAを腸に注入するか、これを生産する大腸菌を食べさせればいい。線虫はRNAを鋳型にしてRNAを合成できるので、導入されたRNAは増幅されて体内に広がり、様々な組織で目的のmRNAを不活化する。ただし、ノックアウトに比べると不正確で、目的のmRNAと似た配列の異なるmRNAも不活化する恐れがある。
調節領域の機能(担当の遺伝子をいつ、どの細胞で発現させるか)を調べるには、その調節領域の支配下のタンパク質に蛍光タンパクの配列を付け加えればよい。調節領域が発現に転じたら蛍光を発すようになるので、蛍光顕微鏡で検出できる。調節領域の支配下にあった元々のタンパク質は蛍光タンパクが連結された状態で生成されるが、たいてい正常に機能する。
ある時点で細胞が持っている多数のmRNAを同時に調べることが可能である。DNAマイクロアレイ法では、まずガラス上に数百種類の50塩基対ほどのDNAを滴下・固定する。mRNAを細胞から抽出して逆転写酵素と蛍光標識プライマーも用いてcDNAに変換し、アレイに流す。ガラス上の光った位置により、どのmRNAが存在したかが判明する。
ある転写調節因子がどの調節領域に結合しているかを調べるには、クロマチン免疫沈降法を用いる。この方法の鍵は、調節タンパクとそれが結合してるDNAをホルムアルデヒドで架橋して固定する操作である。その後に、DNAを断片化して興味ある調節タンパクに結合する抗体を用いて、調節タンパクを結合していたDNAごと精製することができる。同様にして、特定の修飾ヒストンもそれに巻き付いているDNAごと単離して調べることができる。