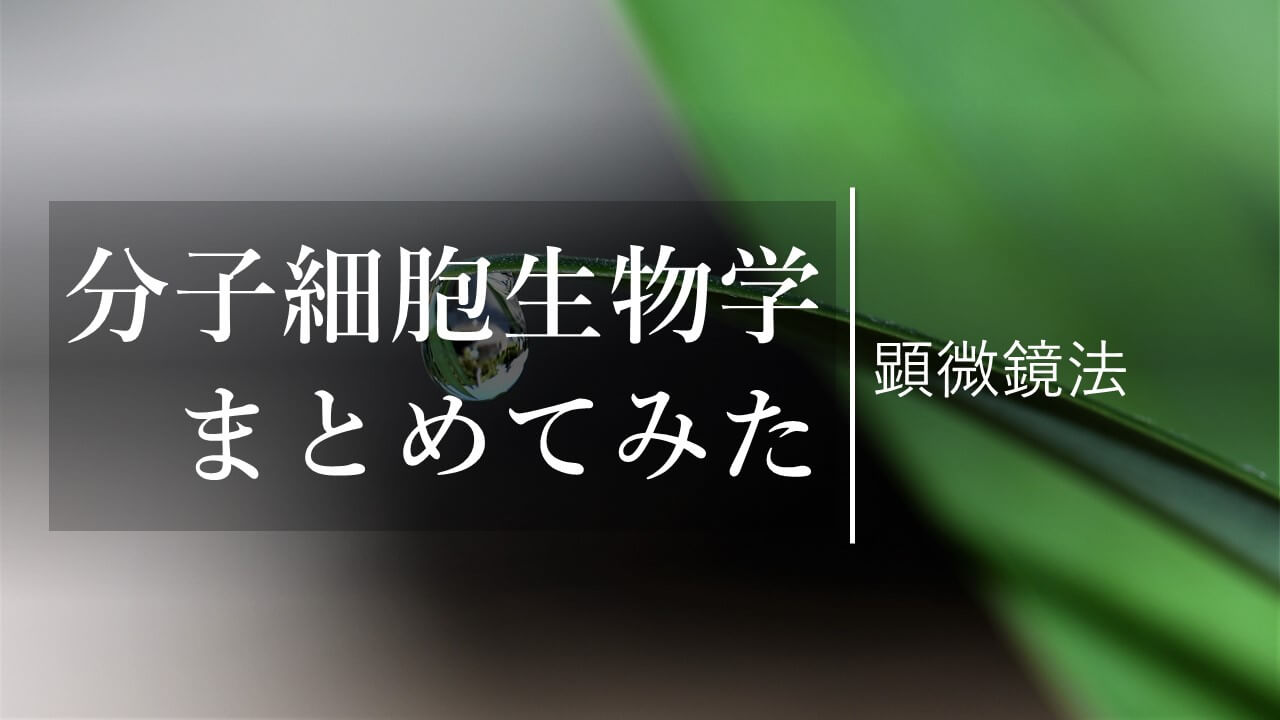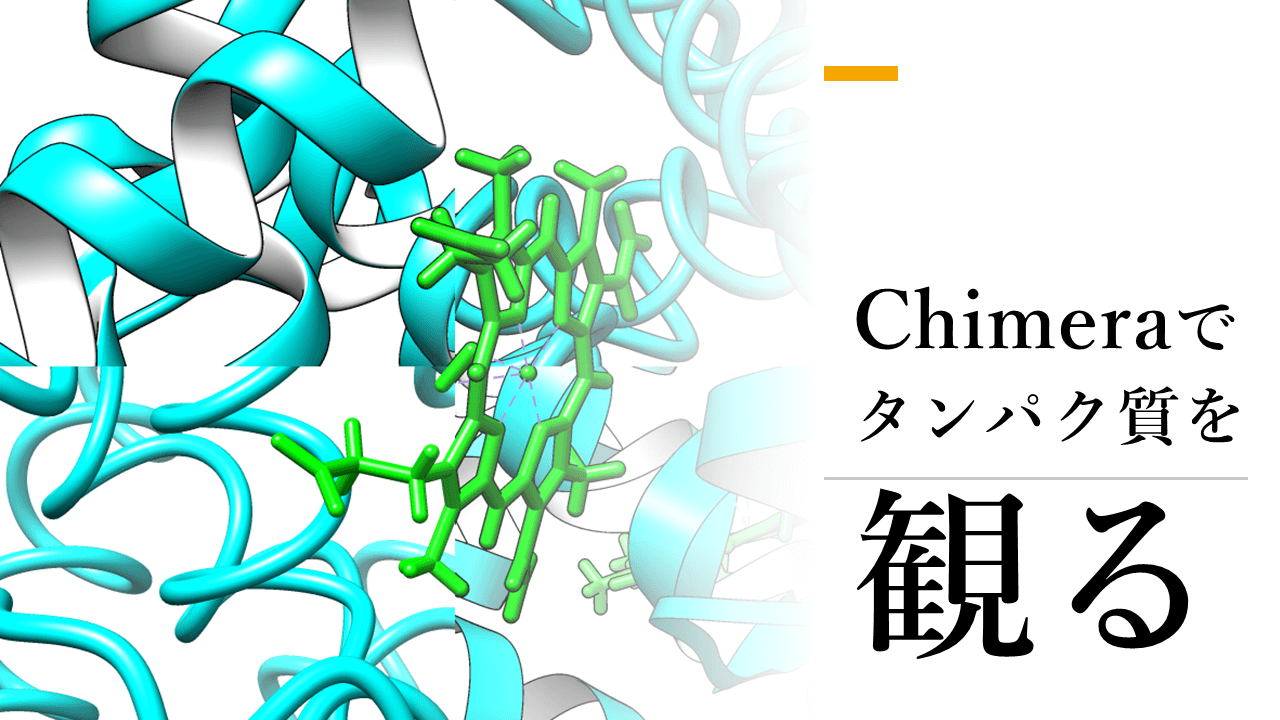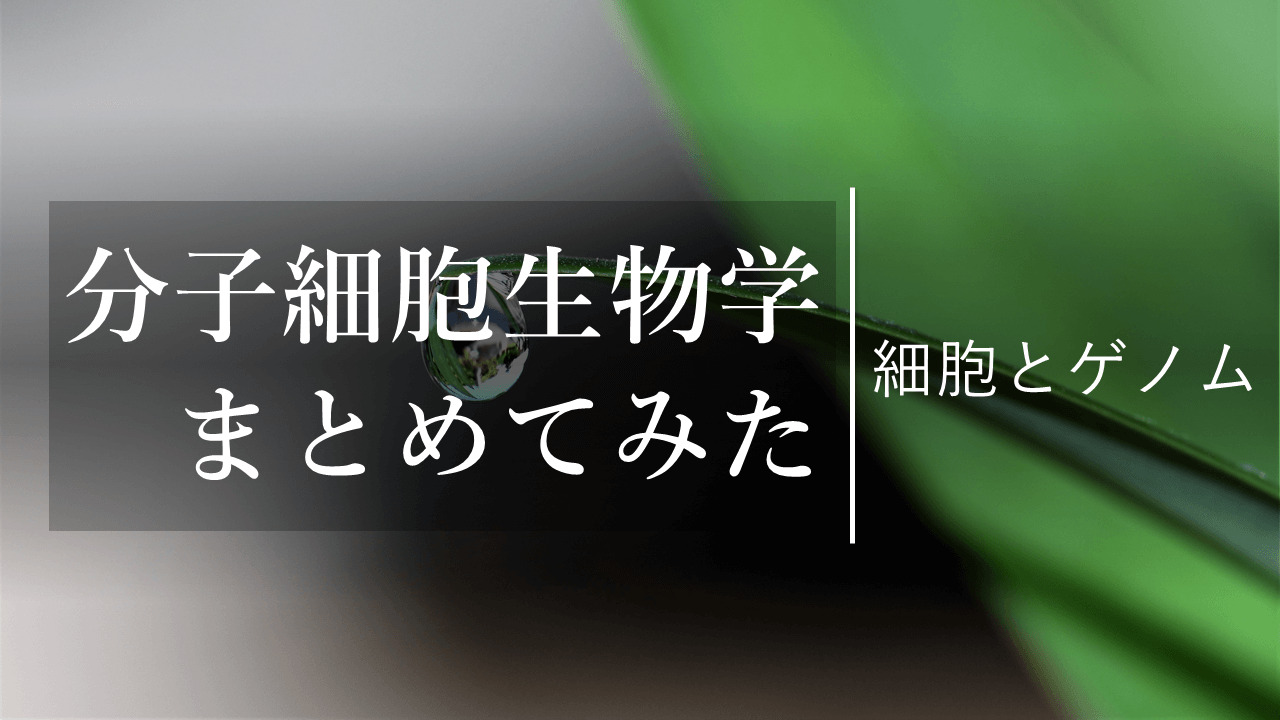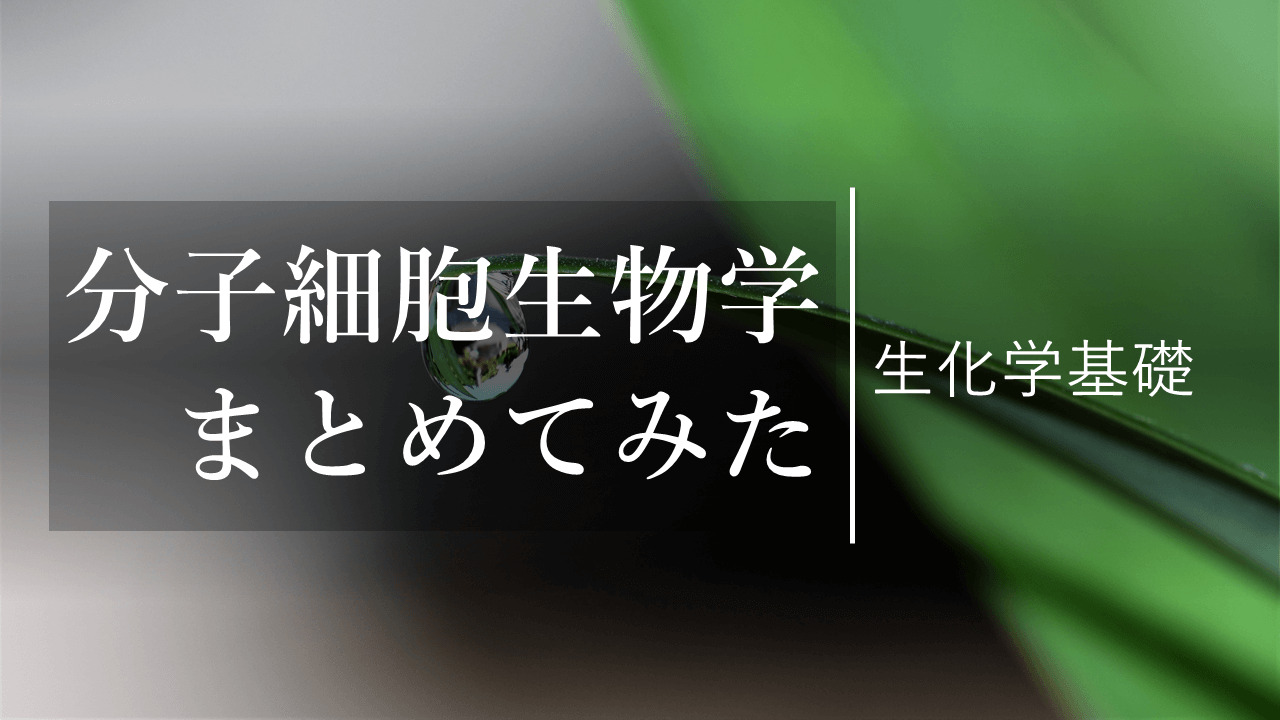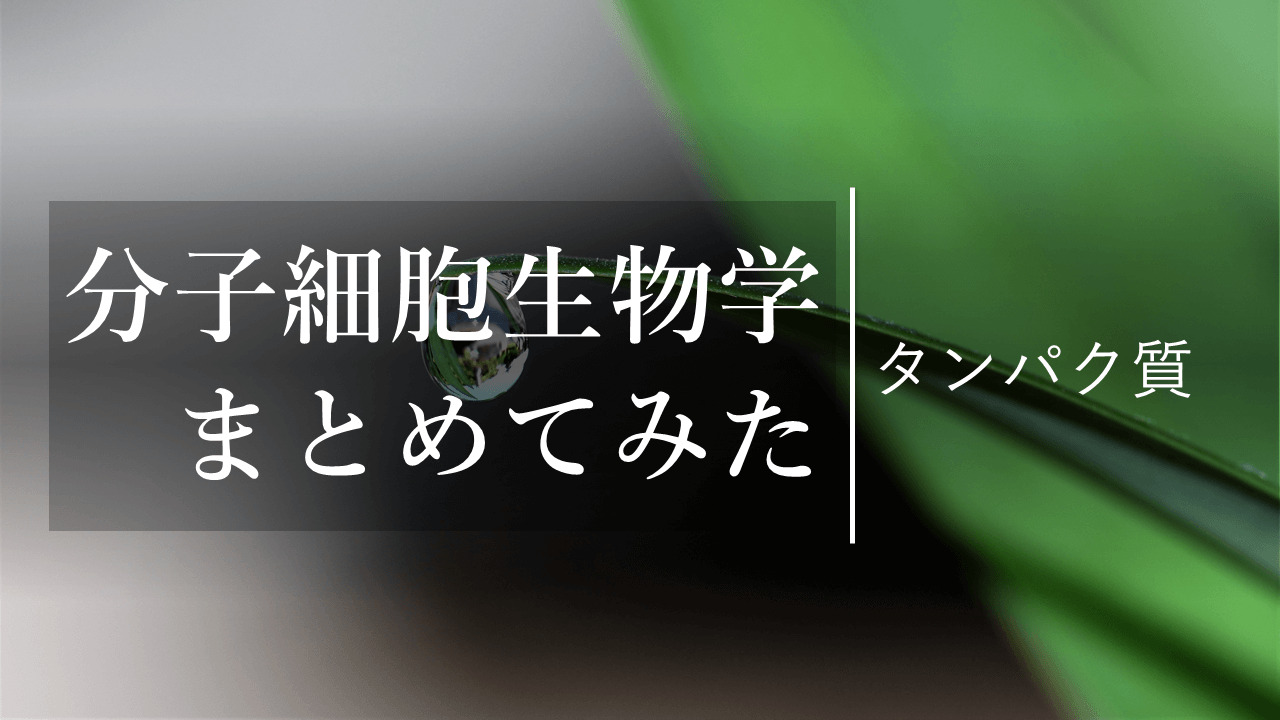顕微鏡法
光学顕微鏡
細胞は直径が約10~20μmで、これは肉眼で見ることができる最小粒子の1/5程度しかない。細胞説が唱えられるには、必然的に光学顕微鏡の発明を待たねばならなかった。細胞は透明なので、内部構造を詳しく観察できるようになるのは染色技術が十分発展してからである。
光学顕微鏡には、可視光の波長より小さなものは見ることができないという物理的な限界がある。光の干渉により、物体の境界がぼやけ、点光源も一定の大きさ以上に見える。普通の光学顕微鏡の解像限界(2点を2点だと識別できる最短距離)は200nmとされている。(200nmはリボソーム10個分くらい)
普通の光学顕微鏡は奥から光をまっすぐ当てて、試料を透過した光を観察する明視野顕微鏡である。この他に、試料に横から光を当てて散乱した光を観察する暗視野顕微鏡、透過した光の位相を明るさに変換する位相差顕微鏡・微分干渉顕微鏡などのより込み入った光学系を持つ顕微鏡が多数開発されてきた。近年はデジタルカメラと画像処理技術を駆使して、肉眼では区別できない小さな違いも検出できる。
組織を光学顕微鏡で観察するには、まず冷却か化学的処理かによって試料を固定しこれを薄切りにする。しかし、このままでは透明でほとんど何も見えないので、特定の分子に親和性を示す色素や蛍光分子で色をつけて観察する。特に蛍光標識や蛍光顕微鏡を組み合わせる方法は、特定のタンパク質の位置を高い感度で突き止めることができる。
蛍光顕微鏡
蛍光顕微鏡は入射光と検出する光の波長を指定して観察する。特定の分子に結合する抗体に蛍光色素を結合させておき、これを細胞に注入すれば興味ある分子の細胞内での分布を知ることができる。目的のタンパクに結合する蛍光分子を外部から注入する以外に、蛍光タンパクが連結した目的タンパクを細胞に作らせる方法がある。目的タンパクの遺伝子の後ろに蛍光タンパクの遺伝子を挿入したDNAを細胞にいれれば良い。蛍光タンパクが融合しても、大抵は元の機能を邪魔しない。この手法は、目的タンパクの位置を追跡する以外にも色々な使い方ができる。
- FRET(fluorescence resonance energy transfer):2つの蛍光タンパクの組(A, B)で、Aの蛍光波長がBの励起波長に近い場合、Aの励起波長を当てるとBの蛍光が観測される。これは、Aの励起状態からエネルギーがBに移動して起こる。光子をやり取りしているわけではなく、物理的原理は難しい。FRETは2つの蛍光タンパクが接近しているときしか起こらないので、異なる2つのタンパクにそれぞれAかBを結合させておき、それらが結合するとFRETにより検出できる。
- 光活性化:常に蛍光活性をもつもの以外に、初めは励起光を当てても光らないが、一度強いレーザーパルスを当てると蛍光を発するようになるものもある。
- 光退色後蛍光回復:光活性化とは反対に、レーザーパルスにより蛍光活性を失うものもある。(GFPもそうである)目的タンパクに連結しておいたうえで、細胞の一部の区画を退色させておいて、その区画が元の明るさに戻るまでの時間から、目的タンパクの流入速度を測ることができる。
標的のイオンと結合しているときだけ蛍光を発するイオンセンサーが開発されている。これを使えば、イオンの濃度変化を追跡することができる。
全反射照明蛍光顕微鏡はカバーガラスの向こう側にある試料に対して、手前から全反射が起こり始める臨界角でレーザーを照射する。すると、カバーガラスの向こう側の極めて薄い層にだけ光子が漏れ、その領域の蛍光分子だけが励起される。したがって、薄い単一の層からくる光のみを見るため、ピントの合わない層からの光を排除した鮮明な画像が得られる。
原子間力顕微鏡は、極めて小さくて、鋭く尖った探針が試料の表面から受ける静電気力やファンデルワールス力を検出することで、表面の形状や特性に関する情報が得られる。元々はそういう技術であったが、探針に吸着した分子を移動させたり引っ張ったりすることができ、タンパク質を解きながら折りたたみエネルギーを測定するのにも使われている。
非常に複雑な構成の蛍光顕微鏡と高度な数学的処理により、光子の回折による分解能の限界を克服することに成功した。生物試料では20nm(リボソーム一個分)の分解能が達成されており、非生物試料ではさらに細かい。
電子顕微鏡
光線の代わりにより波長の小さな電子線(λ≒0.004nm)を用いることで、理論上は0.002nmの分解能が出せる。現実的にはレンズの補正の限界、試料の調製や電子線照射による損傷などもろもろあって、生物試料の有効解像度は1nm程度であるが、これでも普通の光学顕微鏡の200倍良い。電子顕微鏡でレンズの役割を果たしているのは電磁石である。
電子顕微鏡の試料を置く場所は真空で無いといけないので、試料は固化しなければならない。加えて、電子線は透過力が弱いので、極めて薄い切片にしなければならない。主要な処理方法では、試料を脱水した後に、ポリマーの単量体を染み込ませて重合させたり、細胞を急速冷凍させたりする。
電子顕微鏡での写りやすさは、電子密度で決まる。生体を構成する小さくて軽い元素は電子をあまり散乱しないので見えづらい。よく見えるようにするには、U、Pb、Osなどの重金属で”染色”する。染色度合いは成分によって異なり、例えば脂質はOsによって暗く染まる。
蛍光色素付き抗体と蛍光顕微鏡で、細胞内の特定の成分を可視化するように、重元素付き抗体を用いれば、電子顕微鏡でも同じことができる。金コロイド粒子(直径1nm)がよく使われるので、免疫金電子顕微鏡法を呼ばれる。よくある手法では、標的と結合する一次抗体と一次抗体に結合する金標識付き二次抗体を使う。
電子顕微鏡は三次元試料のどの層にも焦点をあわせる事ができる。(切片試料も電子顕微鏡の解像限界に比べればかなり分厚い)様々な深度の像や連続切片の像から、もとの試料の三次元構造を再現する事ができる。
電子顕微鏡は走査型と透過型の2種類ある。透過型は試料を透過してきた電子線を検出するタイプで、分解能が良い。走査型は試料の表面で散乱、もしくは発生した電子線で像を作る。走査型のほうが小型で廉価であるが、表面の情報しか得られない。走査型の分解能は近年では向上しており、透過型に引けを取らない。