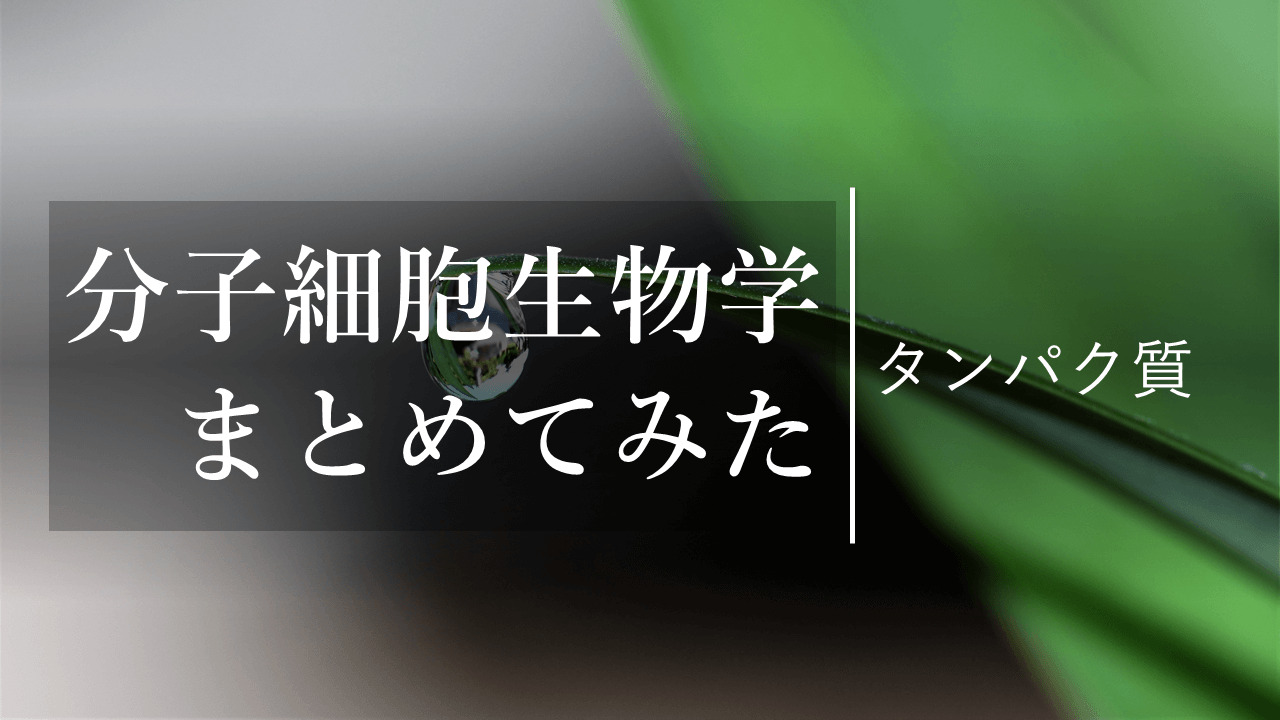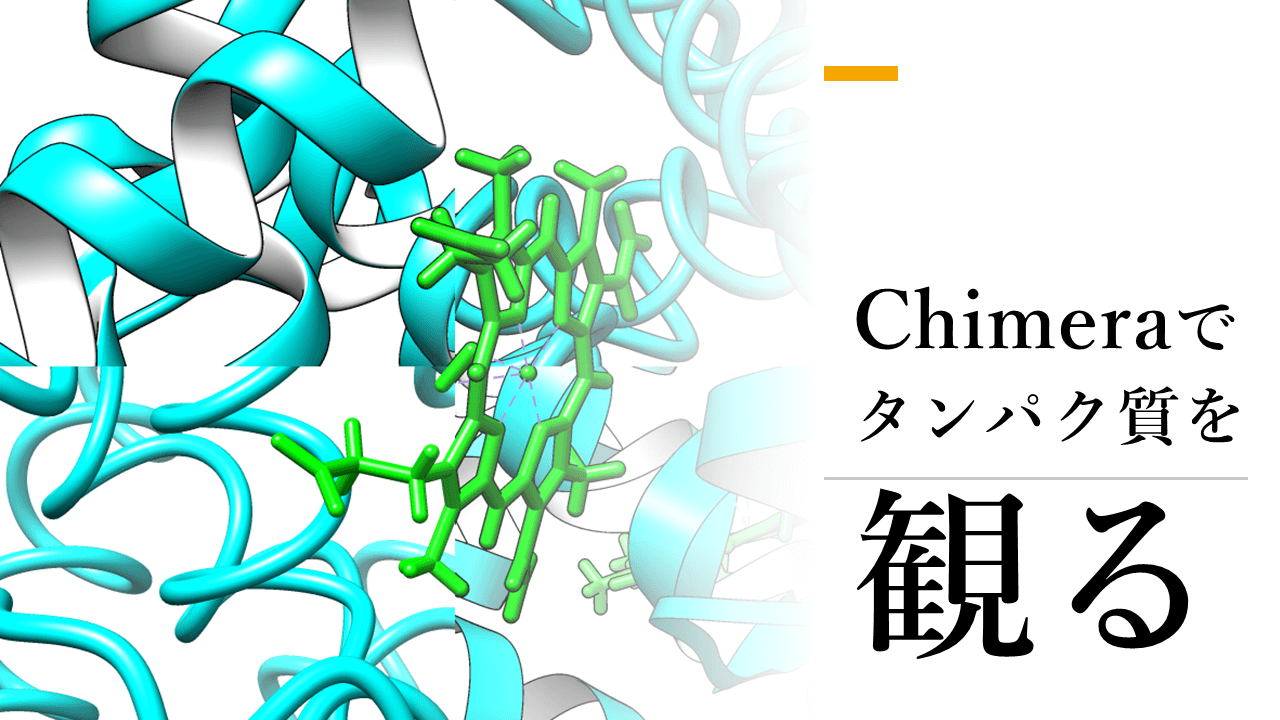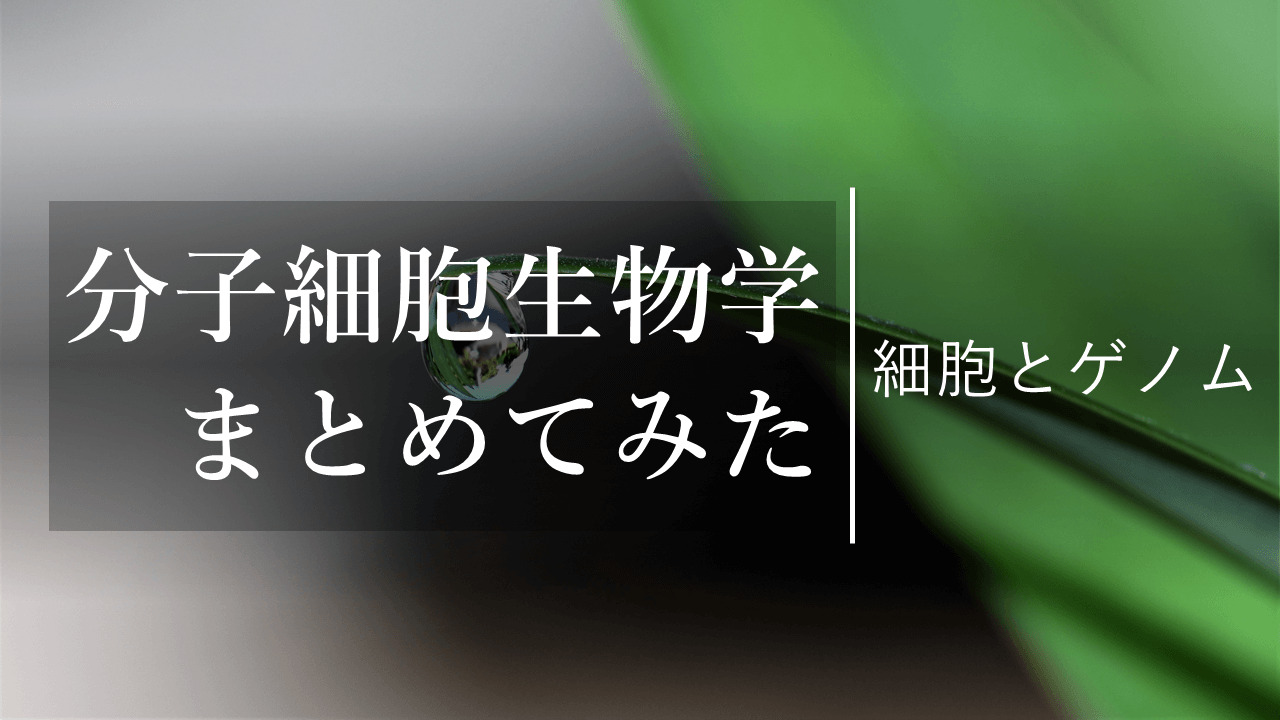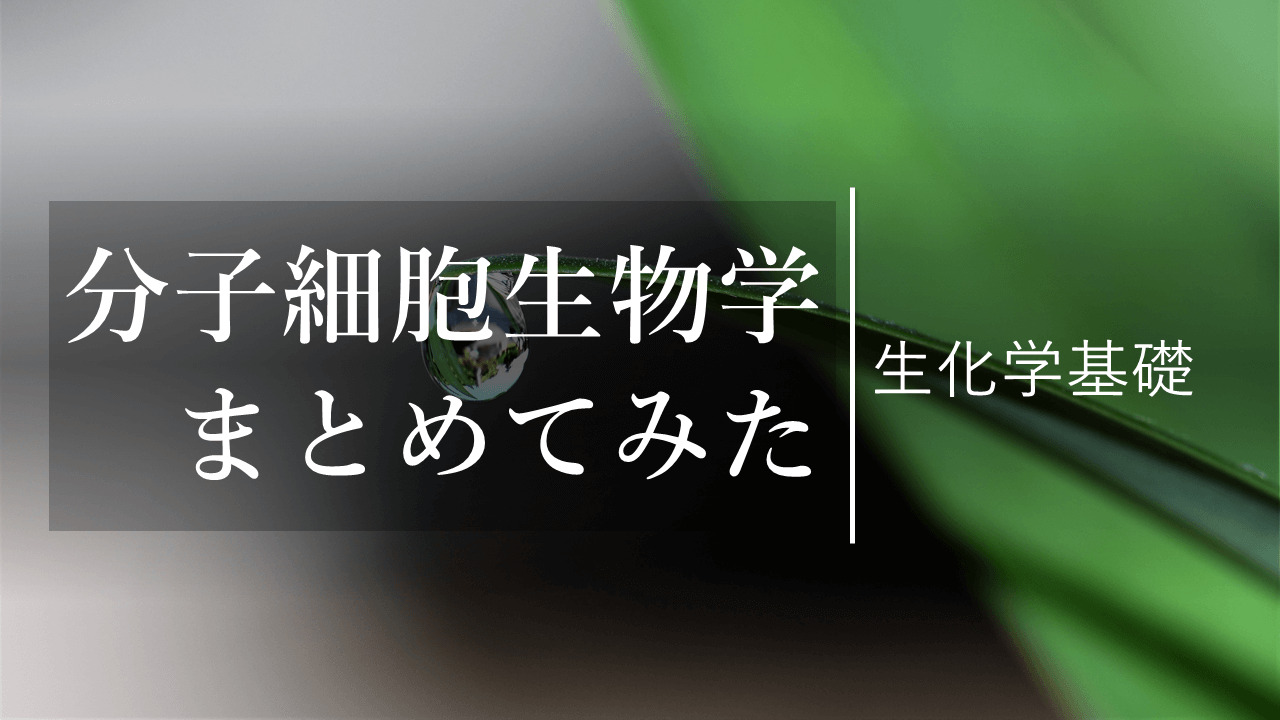タンパク質
タンパク質の構造
- 1次構造:アミド結合
- 2次構造:主鎖同士の水素結合
- 3次構造:側鎖によるイオン結合、水素結合、共有結合(ジスルフィド結合など)、ファンデルワールス結合
- 4次構造:サブユニット表面同士のイオン結合、水素結合、ファンデルワールス結合など
2次構造は主鎖によるものなので、原理的にはどのアミノ酸配列でもαヘリックス、βシートが作れるが、側鎖同士がぶつからないような配置にならなければならず、アミノ酸によってどっちができやすいか大体決まっている。
タンパク質は細胞内環境中で安定な構造をとる。いくつか安定な構造があったとして、目的の機能を発揮する構造が最安定なものでなければ、勝手に別の最安定構造に変化してしまい、使い勝手が悪いだろう。そのような配列は進化の過程で淘汰されたと考えられる。全ての可能なペプチド配列のうち、決まった構造を取れる配列は10億に1つもないらしい。したがって、遺伝子重複によって、まともな構造をとることが保証されている既存のタンパク質のコピーから変異させていくのは合理的である。
ドメインという構造次元:独立して折りたたまれる領域で、特定の機能を持ち、様々なタンパク質で共通して見られる。上の分類だと2.5次構造に相当する。ドメイン単位でDNAがコピーされている例がたくさん見つかるのは、ドメインを割るようなコピーからは有用な遺伝子は生じづらかったことが理由かもしれない。(極端な場合、構造をとらない)
4次構造:タンパク質どうしで、表面の形や電荷、水素結合のドナー・アクセプターなどが相補的なら、2つのタンパク質はその面を合わせるようにくっつくことで安定化する。ヘモグロビン、アクチンフィラメントなどが例。こういった構造では、複合体全体が繊維状でも構成単位であるタンパク質自体は球形であることが多い。中には3次構造の時点で細長いものも存在する。
側鎖同士が結ぶジスルフィド結合は、それがなくても安定な構造を補強するためのものであって、ジスルフィド結合がなければ成立しないような構造にするためではない。そもそも細胞の中は還元的な環境なので、ジスルフィド結合は安定でなく、主に細胞外に放出するタンパク質の寿命を上げるために使われる。涙に含まれるリゾチーム(殺菌作用)などが例。
タンパク質は他の分子と相互作用して結合することで機能を発揮する。このとき働くのは、ほとんど非共有結合である。
| 結合の種類 | 典型的な結合強度 |
| 共有結合 | 350kJ/mol以上 |
| イオン結合 | 12.6kJ/mol |
| 水素結合 | 4.2kJ/mol |
| ファン・デル・ワールス結合 | 0.4kJ/mol |
ランダムコイル
明確な構造を持たない領域(ランダムコイルという)は、取りうるあらゆる構造が皆同程度に安定ということだろう。ランダムコイルのある構造は速度論的に高い壁に囲まれておらず、体温的な環境下で同程度に安定な構造に素早く変形することができる。ポテンシャル曲面が微妙に凹凸のある平原のようになっていて、ほぼ連続的に可能な構造が存在している。縮んだ構造が伸びた構造に比べて程よく安定な場合、そのペプチドは弾性を示す。(e.g. エラスチン)この性質のおかげで、皮膚や血管、肺などは、膨らんでも破れない。
普段は明確な構造を持たないが、他のタンパク質と非共有結合しているときだけ構造が決まるランダムコイルが存在する。この領域のいくつかの残基がリン酸化されると、そのタンパク質と結合しなくなり、ランダムコイルに戻るといった調節がなされることもある。
2つのドメインをつないでいる領域(リンカー)はランダムコイルで有ることが多い。また、ランダムコイルがたくさん集まっている空間はゲル状になり、他のタンパク質が拡散しづらくなる。(核膜孔など)
タンパク複合体
タンパクサブユニットが集合してできる複合体は、基本的に自己集合する。(構造を維持する為だけに自由エネルギーを消費し続けるのは確かによろしくない)したがって、構成部品を個別に合成して混ぜると自動的に複合体が組み上がる。
- リボソーム:55種類のタンパク分子と3種類のRNAを混ぜて放っておくと、自動的にリボソームに組み上がる。
- トマト萎縮病ウイルス:180個のタンパク質と1本のRNAから、完全な感染力のあるウイルス粒子が出来上がる。
- タバコモザイクウイルス:1本のRNAを正確に2130個のタンパク質が螺旋状に覆った構造の粒子。
こういった複合体は、溶液中でバラバラに存在するよりも、集合体を形成するほうがエネルギー的に有利なのである。
集合体構造が熱力学的に安定だが、速度論的にたどり着くのが困難であるか、最終的な形に至るためにいくつかの共有結合が切れなければならない場合がある。このような場合、ポリペプチドは単独では完成形になることはできず、他の酵素による手助けが必要である。
アミロイドという、比較的安定な誤った折りたたまれ方に陥るタンパク質がある。アミロイドは特定のタンパク質の名前ではなく、そのような誤った構造をとったタンパク全般を指す言葉である。アミロイドは凝集して繊維を作る性質があり、それまで正しい構造をとっていたタンパク分子をも誤った構造に導く。これが正のフィードバックとなって、アミロイド繊維が成長する。アミロイド繊維は、アルツハイマー病などの原因となっている。
細胞がアミロイドを制御して使う場合もある。可逆性アミロイドと呼ばれ、シグナルに応じてくっついたり離れたりする。一時的な構造体を作ったり、低複雑度領域(ランダムコイルのこと)がゆるやかに会合してゲル状になったりする。こうしたゲルはチロシンやセリンなどのヒドロキシ基から成っており、ここをリン酸化することでゲルの性質を制御できると考えられる。
酵素
酵素が生化学反応を触媒するやり方:反応の遷移状態を安定化するような反応場を提供して、基質に楽な反応経路を与える。酵素表面の形、電荷分布、水素結合の受容体・供与体などの配置が、目的の遷移状態を安定化するために重要な役割を果たすので、アミノ酸の配列がわずかに変わるだけで、もはや目的の遷移状態を安定化できなくなる場合がある。
タンパク質同士が結合するときも、表面の相補性が重要となる。水素結合が2、3個減っただけで親和性に大きな影響を及ぼす。反応自由エネルギーの変化は平衡定数の対数と線形であることを思い出そう。平衡定数はエネルギー変化の指数に比例する。
酵素は有機化学で言うところの酸触媒と塩基触媒の役割を同時に果たすことができる。例えば、塩基性残基の共役酸が基質のカルボニルの酸素付近に位置してこのカルボニルの極性を高めると同時に(酸触媒)、酸性残基の負電荷を帯びた共役塩基が水分子のプロトンを引っ張り、ほとんどOH-としてカルボニル炭素に攻撃させる(塩基触媒)、といったことが行われる。
- 共役酸:塩基がプロトンを受け入れた形。例えばグルタミンの側鎖のアミノ基にプロトンが配位して、-NH3+となったもの。
- 共役塩基:酸からプロトンが放出された形。グルタミン酸のカルボン酸がプロトンを一個放出して-COO–となった物など。
補酵素:酵素に非共有結合して共に反応を触媒する小分子。単に酵素表面の形を変えるアタッチメントとしての役割だけでなく、置換基や自由エネルギーを持ち込むことが多い。ATPも補酵素の一員。補酵素の多くはビタミン類から合成される。また、金属イオンも補酵素として使用されることがある。
酵素の触媒する反応の速さはとても速いので、酵素反応の全体の速度はほとんど酵素と基質が出会う速さで決まる。いくつかの連続する反応を触媒する酵素たちが集まって酵素複合体を形成する場合、基質を次々と複合体内で回すことで基質との出会いをある程度省略可能なため、全体の反応速度が上がる。実はほとんどの酵素は何らかの複合体の部品となっており、むしろ細胞質を単独で浮遊している酵素のほうが稀である。また、小胞内に特定の基質と酵素群を閉じ込めて、濃縮するという手法を用いることもある。
酵素反応の調節
酵素反応の調節の仕方にはいろいろある
- 遺伝子の発現を調節して酵素を作る速度を変える
- 酵素を切断・分解して酵素数を減らす
- 酵素に小分子(リン酸など)を共有結合させ酵素の安定な配座を変え、反応を触媒できなく(できるように)する
- 酵素の活性部位に小分子を非共有結合させ反応を触媒できなく(できるように)する
酵素によって生産された分子が自身を合成する反応を調節する方法はフィードバックと呼ばれ、細胞内で多用される。フィードバックの効果は素早く、ほぼ瞬間的に働くと考えて良い。
アロステリック調節:多くのタンパク質は2つ以上の分子と相互作用する。タンパクと結合しうる2つの基質AとBが、①そのタンパクの異なる配座と結合しやすい場合と、②同じ配座と結合しやすい場合がある。①の場合は2つの基質が酵素を取り合う形になる。つまり、酵素はAと結合している時にはBと結合しにくくなり、逆もまた然り。一方②の場合は、2つの基質は互いに相手と酵素の親和性を高め合う。
例えば4量体の酵素で、基質結合型は結合型同士で、未結合型は未結合型同士で集合するのが安定だとする。このとき、4量体全体としての活性は全か無かの調節に近づく。中途半端に1つか2つが結合状態になるよりは、1つも結合しないほうがエネルギー的に有利だからである。ヘモグロビンはこの種の調節を利用して、酸素が豊富なところでは全てのサブユニットが酸素を結合し、酸素が不足しているところでは全てのサブユニットが酸素を開放するという効率の良い仕事をなしている。
チロシン、セリン、トレオニンのヒドロキシ基にリン酸を付加するという化学反応がよく見られる。リン酸基は2価の負電荷を持つため、近隣の正電荷を持つ基を強く引き寄せて、タンパク質の配座を大きく変える事がある。SH2ドメインはリン酸化チロシンの構造と非共有結合するので、あるタンパク中のチロシンがリン酸化されると、他のタンパクのSH2ドメインと相互作用するようになる。反対に、リン酸化によってタンパク表面の構造が変化し、それまで安定だった複合体はさほど安定ではなくなり、複合体が乖離することもある。リン酸化するタンパク質はキナーゼと呼ばれ、ATPを使ってリン酸化する。一方脱リン酸化はホスファターゼが触媒する。
キナーゼがタンパクをリン酸化するためには、キナーゼ自身がリン酸化されないといけない、という場合がある。もし、このキナーゼの活性化が2つのリン酸化によって達成されるとしたら、このキナーゼはAND回路のような働きをしていると言える。つまりこのキナーゼは、自身をリン酸化する2つのキナーゼがともに活性状態のときに活性化するのだ。このように、細胞内におけるシグナル伝達回路は、論理演算回路に見立てることができる。
様々なタンパク質
GTP結合タンパクは大きなファミリーを成し、タンパクが直接リン酸化されるのではなく、結合しているGTPがGDPになったり、GDPが乖離して新しいGTPが結合するなどして活性が変化する。GTPとGDPの持つリン酸基の数と位置が異なることにより、タンパク中の電荷を帯びた部分の配置が変化して全体の構造が変わるという仕組みである。ほとんどの場合、GTP結合型が活性型、GDP結合型が不活性型である。
GTP結合タンパクの例を一つ:ET-Tu:これはtRNAを補足しリボソーム(翻訳酵素)に受け渡すタンパク質である。補足しているtRNAのアンチコドンとmRNAのコドンがぴったり一致したときに、tRNAがリボソーム側にわずかに引っ張られ、このときの構造変化によりET-Tu内のGTPが加水分解が誘発される。この反応は、リン酸が遊離するというエネルギー的に有利な反応であるから、不可逆的に進行する。すると、ET-Tuにあるスイッチヘリックス(双極子モーメントを持つヘリックス)がGTP→GDPの電荷の変化により位置を変え、このことによりET-Tuは補足していたtRNAを完全に離す。このようにしてtRNAがリボソームに移ると、そこに結合していたアミノ酸は伸長中のポリペプチド鎖に転移できるようになる。
ユビキチンはアミノ酸76個からなる小さなタンパク質で、リン酸化のように基質タンパク中のリシンのアミノ基に付加される。ユビキチン自身もリシンを複数持ち、ユビキチンが多数連結した構造(ポリユビキチン)はどのリシンで連結しているかによって、細胞内で異なる意味を持つ。代表的な機能はユビキチン化されたタンパク質をプロテアソームと呼ばれる大型のタンパク質複合体に誘導して、この基質タンパク質を分解させることである。タンパク質やユビキチンにユビキチンを付加するタンパク複合体(ユビキチン連結酵素)は、標的タンパクと触れる部分に使われる部品を取り替えることで、多数の種類のタンパクを補足してこれをユビキチン化できる。このような少しづつ構造の異なる交換可能なサブユニットは、進化の途中で遺伝子重複によって生じたと考えられる。
モータータンパク質はATPを加水分解しながら自身の構造を大きく変化させ、化学的なエネルギーを力学的な仕事に変換する。仕事をしたあとは普通、始めと同じ構造に戻り、次のサイクルを開始できるようになる。細胞内はATPがADPより過剰に保たれているため、この構造の変化は同じ方向にだけ進み続ける、逆反応はまれにしか起こらない。
膜結合輸送体はATPを加水分解するときに生じる自由エネルギーを使って、膜間に濃度差を生んでこれを維持したり、反対に濃度差に蓄えられた自由エネルギーをATPに固定したりする。これらの過程も、タンパク質の構造変化により実現されている。詳しくは、こちらの記事を参照されたい。
タンパク質の特定の残基に、リン酸やユビキチンの他にメチル基やアセチル基などが付加される場合がある。我々人間はシグナルと呼んで、情報や意味が伝達されていると解釈する。しかし、結局は分子の表面の形状(形、電荷分布、水素結合の受容体・供与体の配置)が変化し、それまでは速度論的に起こりづらかった化学反応が体温下で獲得できる程度の活性化エネルギーで起こるようになっただけのことである。